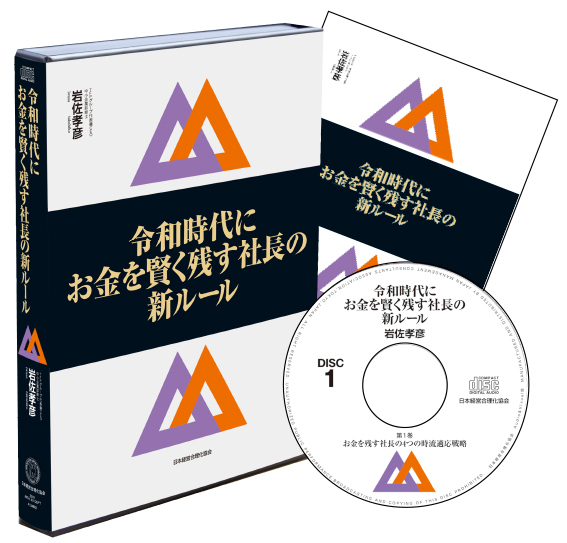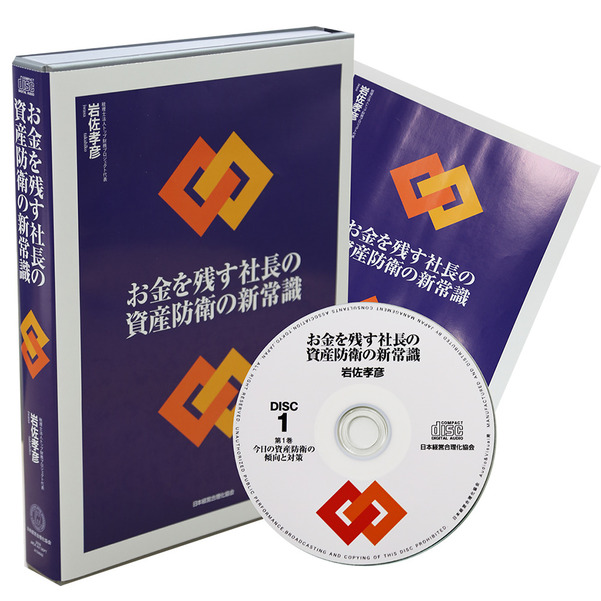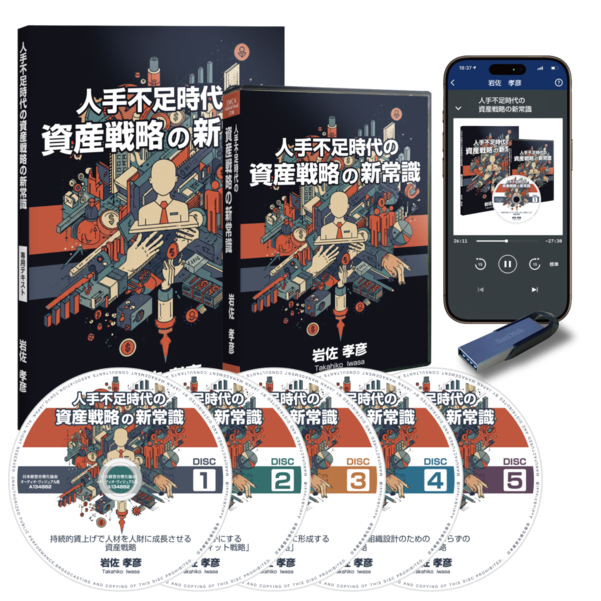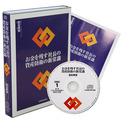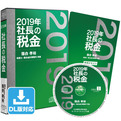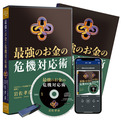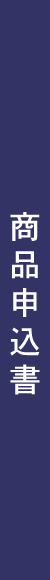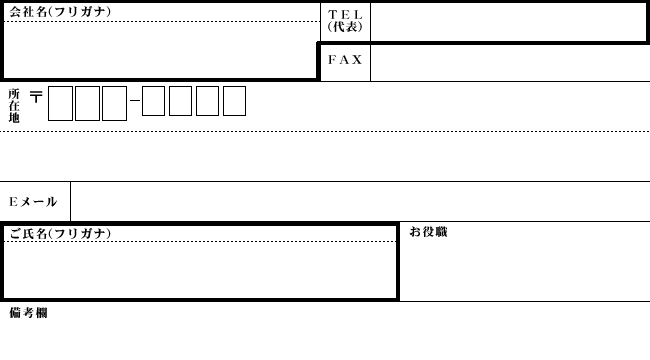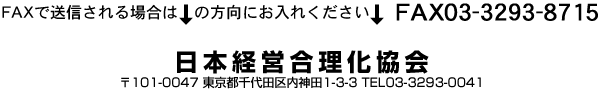岩佐孝彦 (いわさたかひこ)TFPグループ代表兼CEO
1969年兵庫県生まれ。税理士法人トップ財務プロジェクトと社会保険労務士法人トップ労務マネジメントを擁する総合ファームTFPグループを主宰。お金とヒトの両面からワンストップでオーナー経営者を支援し、戦略会計・労務・助成金・事業承継のトータルサポートに高い評価を得ている。クライアントの8割以上が富裕層であり、金融資産1億円以上や年収2,000万円以上の開業医をはじめ、創業175年の五代目社長や創建600年以上の寺院住職など百年企業の経営者が多い。金を残すだけでなく、社員の物心両面の幸福の追求や永続企業の経営基盤づくりにつなげる手法は、全国の社長から絶大な信頼を得ている。
著作として、「お金を残す社長の資産防衛の新常識CD」(日本経営合理化協会)、「社長と会社のお金を残す力“養成”講座」(日経BP社)、「オーナー社長の財務対策4つの急所CD」(日本経営合理化協会)の他多数。日経トップリーダーやプレジデントのメディア実績を有し、講演実績800回以上。