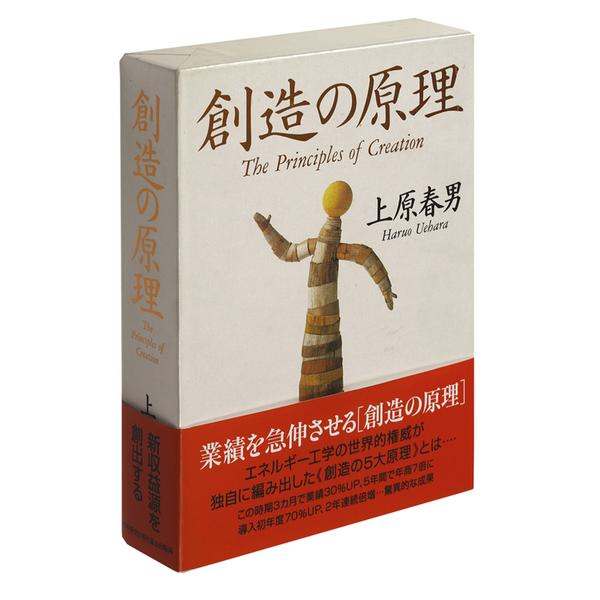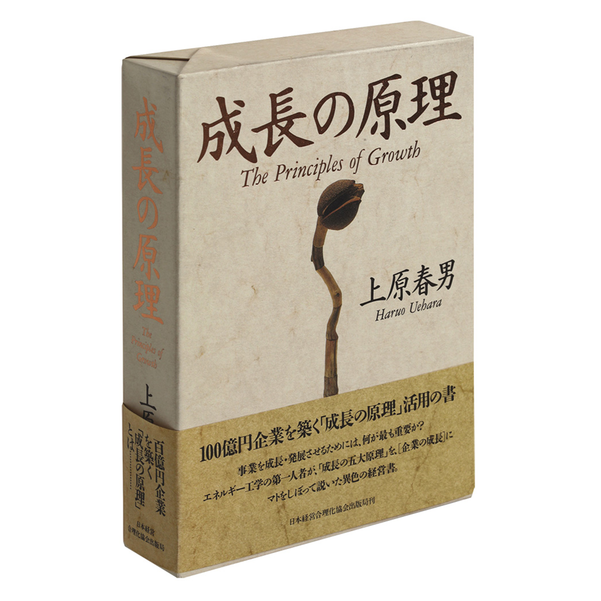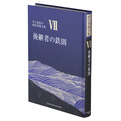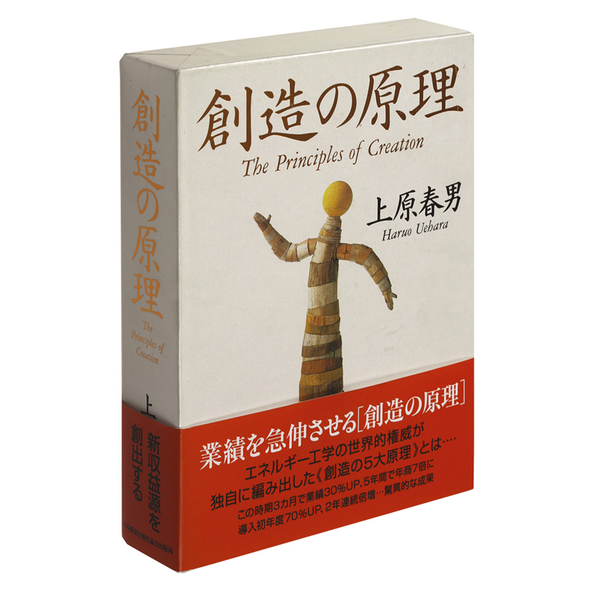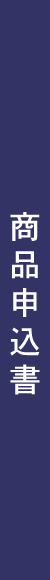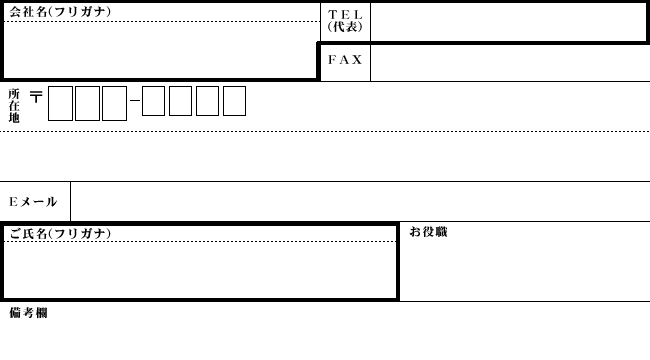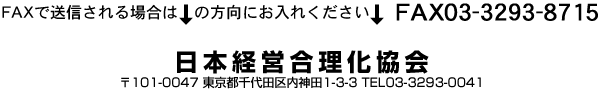上原春男 (うえはらはるお)佐賀大学(前)学長
熱工学の世界的権威。独自に編み出した「創造の原理」によって、「ウエハラサイクル」「ウエハラプレート」はじめ数多くの発明を行い、世界主要国に特許をもつ。氏の設計による世界初の実用型海洋温度差発電所が、2002年からインドで稼働。再生可能な夢のエネルギーがいよいよ実用段階に入り、世界的に注目されている。
1996年、弊会から「成長の原理」を出版、その異色な内容に刺激を受けた全国の経営者が参加して「上原塾」が開かれ、業績を急伸させる経営者が続出。経営においても上原理論の有用さが証明された。物理学者でありながら交友の幅は広く、政治家、官僚、トップ財界人や中小企業の経営者、小説家から陶芸家まで多岐にわたる。工学博士。
《略 歴》
1940年3月 長崎県生まれ
1963年3月 山口大学文理学部理学科(物理学)卒
1963年4月 九州大学生産科学研究所助手
1963年9月 九州大学生産科学研究所講師
1973年4月 佐賀大学理工学部助教授
1985年4月 佐賀大学理工学部教授
1996年4月 佐賀大学理工学部学部長
2002年4月 佐賀大学学長
2003年 佐賀大学海洋エネルギー研究センター教授
2005年 佐賀大学を定年退官、NPO法人海洋温度差発電推進機構を設立
2015年 秋の叙勲で瑞宝中綬章を受章
2017年8月 逝去
《著 書》
「成長の原理」「創造の原理」(日本経営合理化協会)
「風と太陽と海−さわやかな自然エネルギー」(コロナ社)「海洋温度差発電」(産業調査会)、他多数