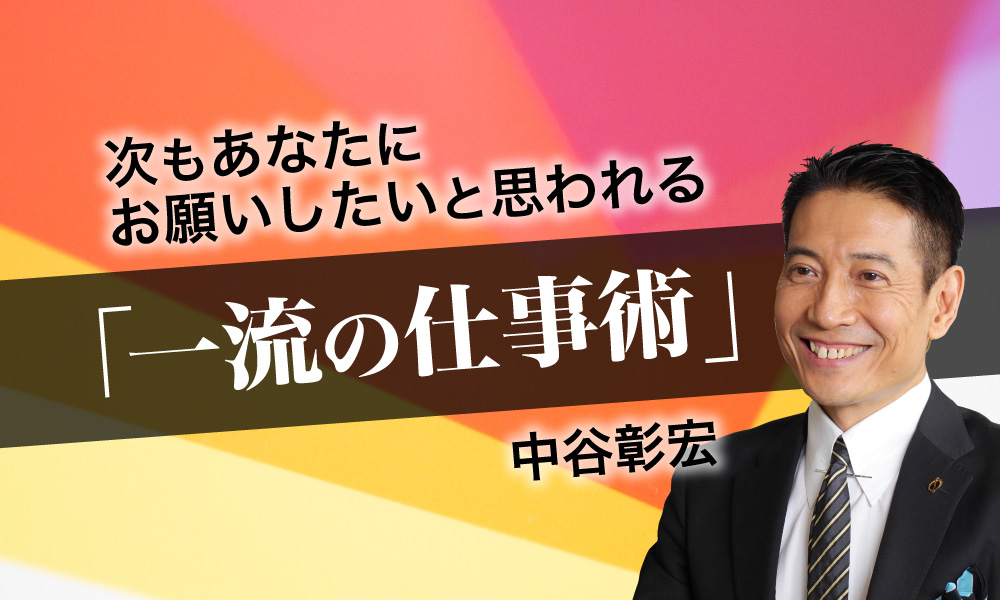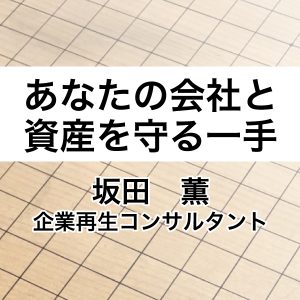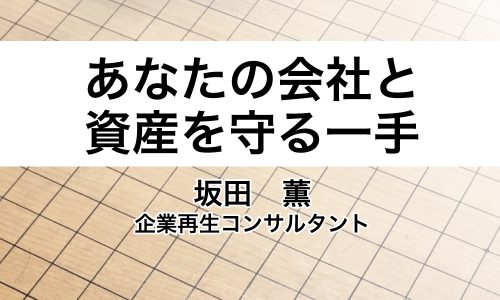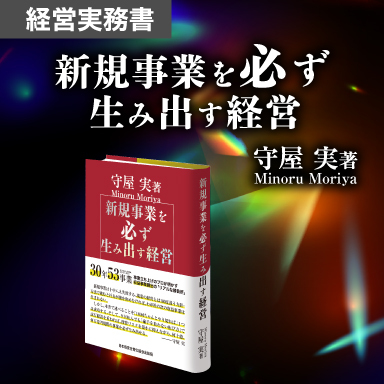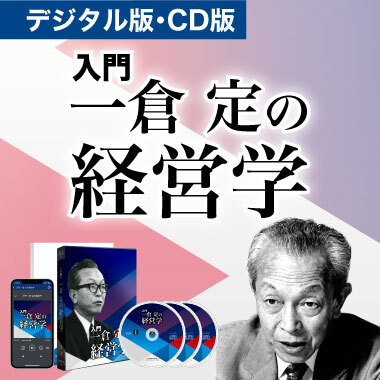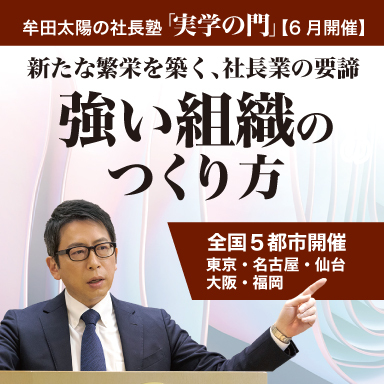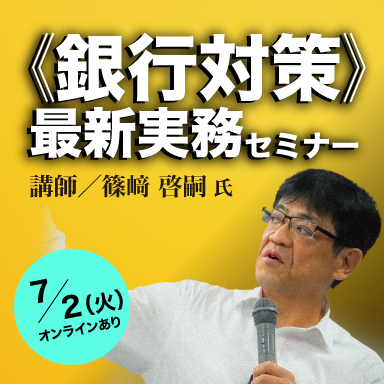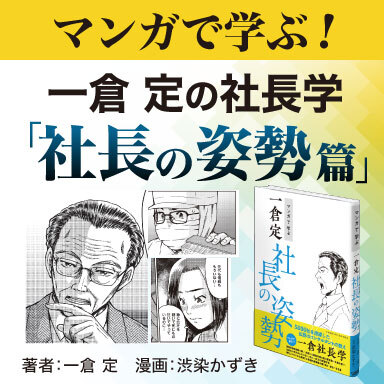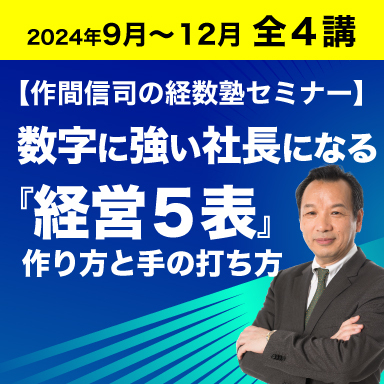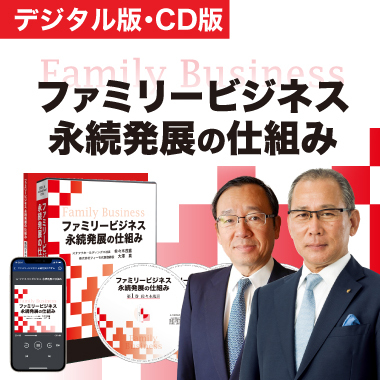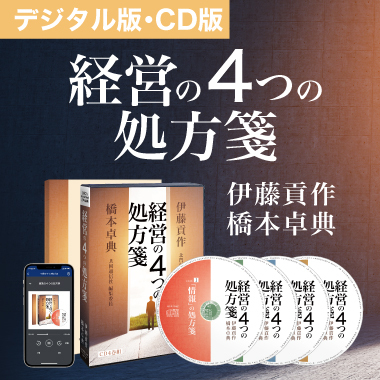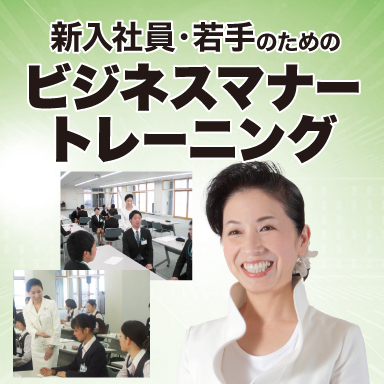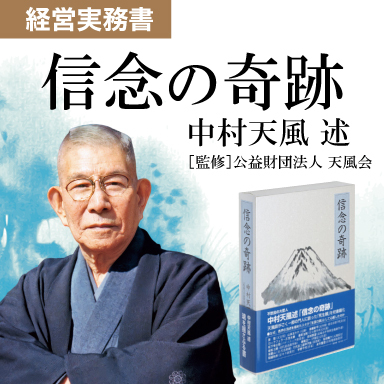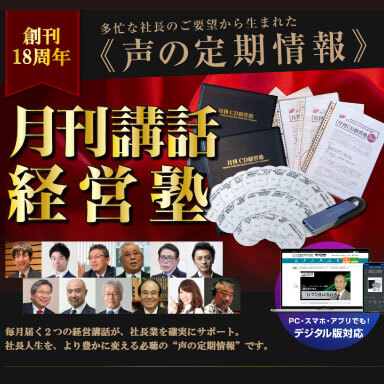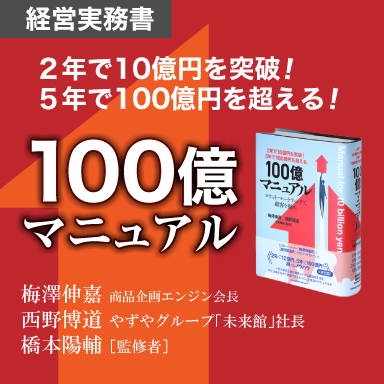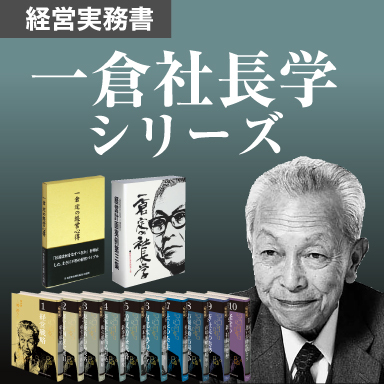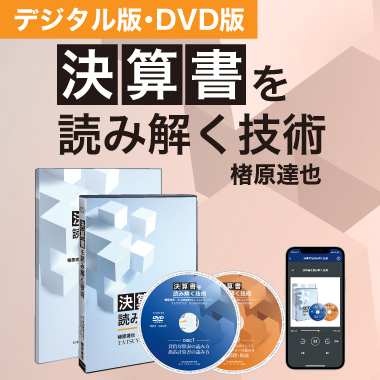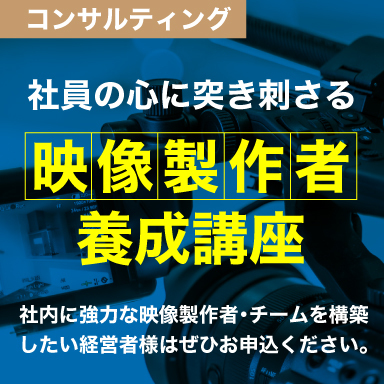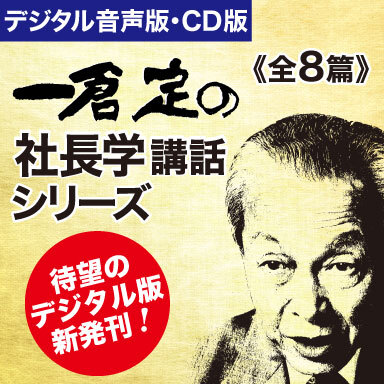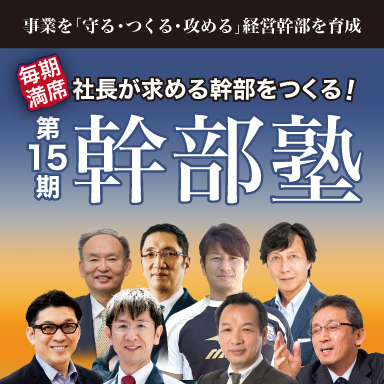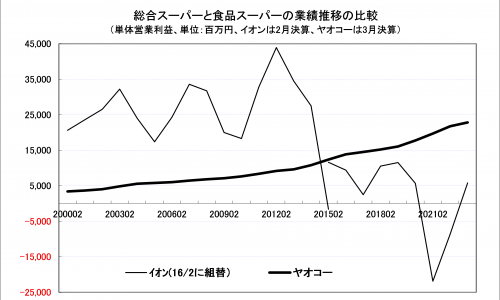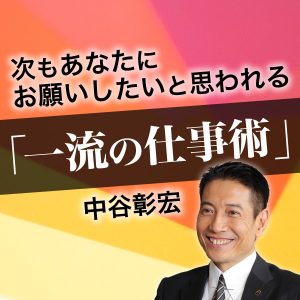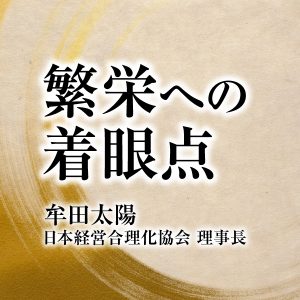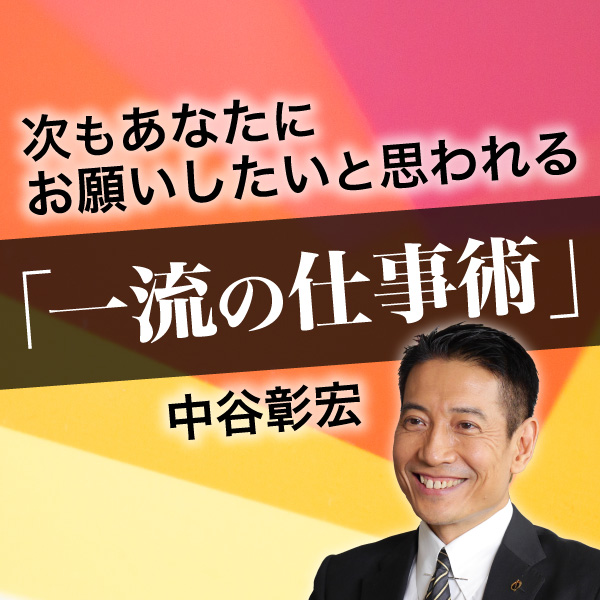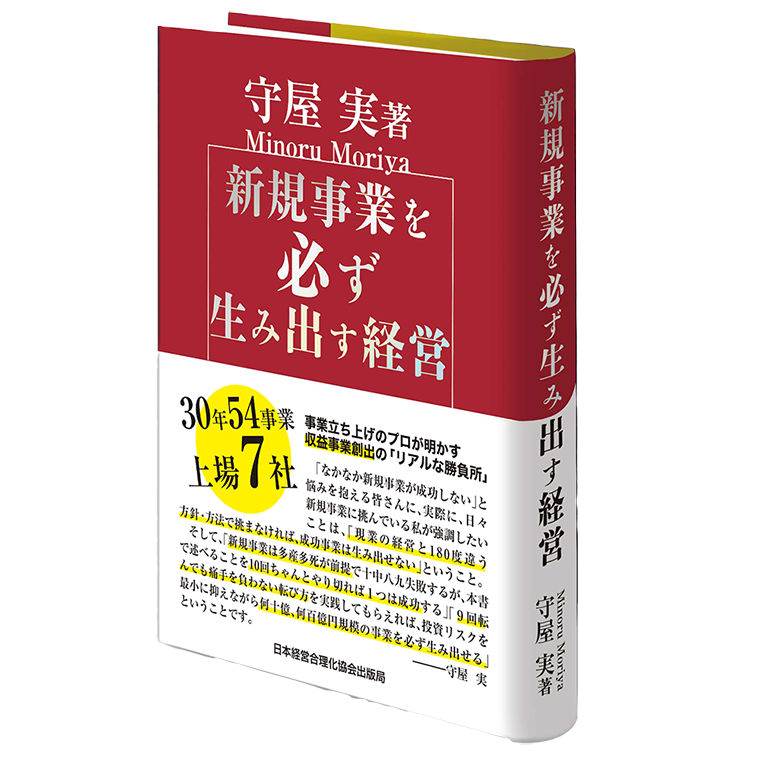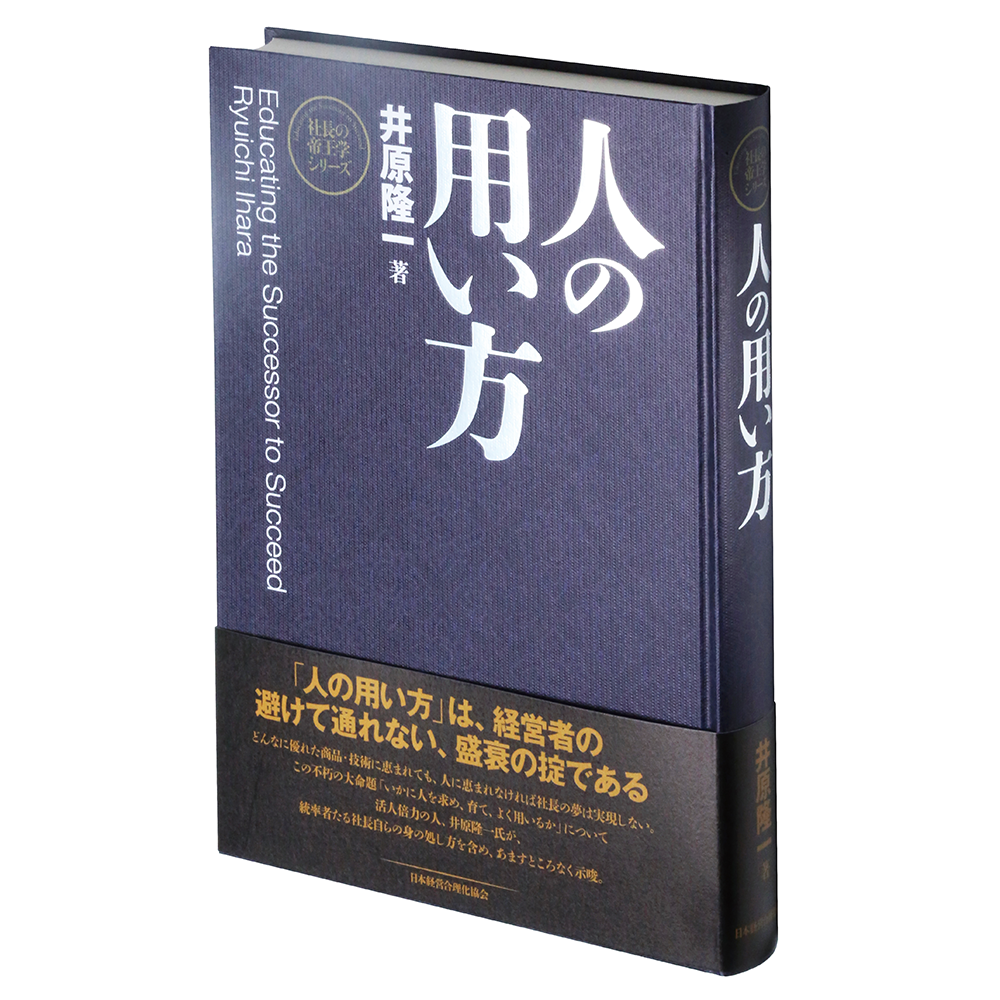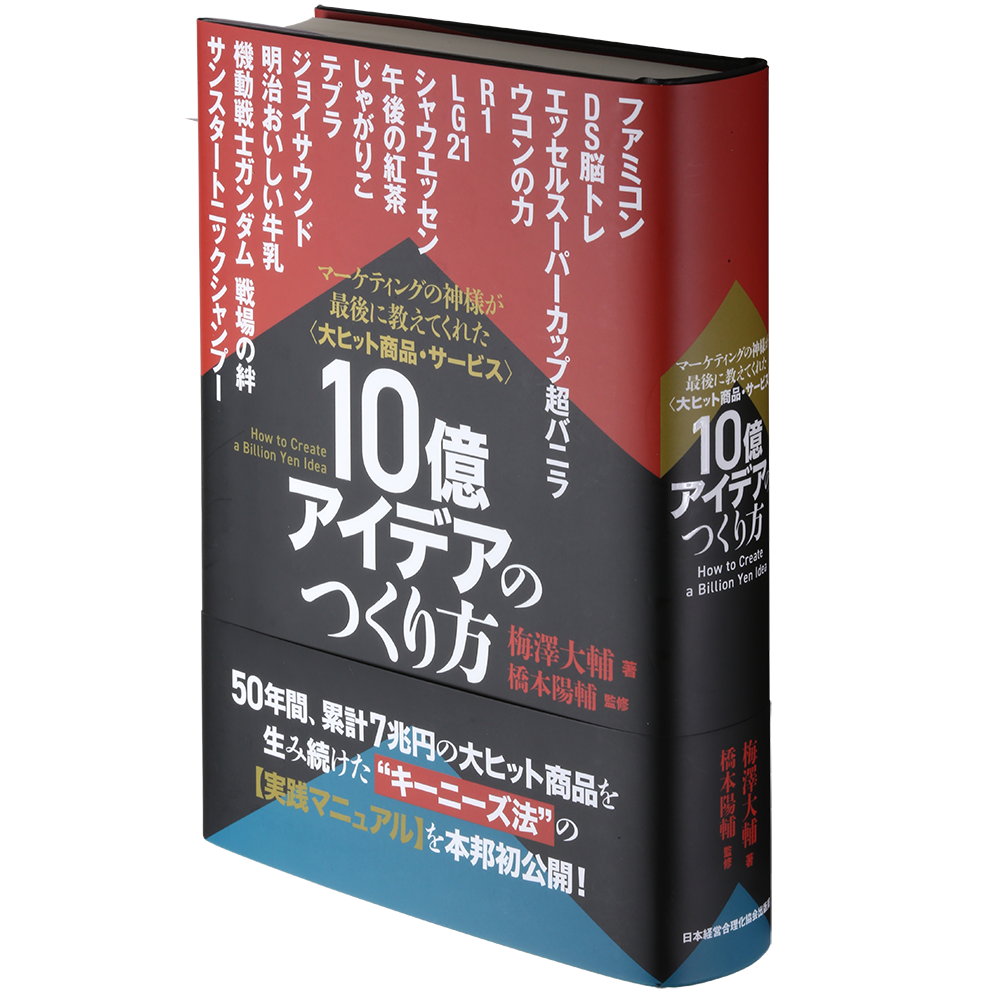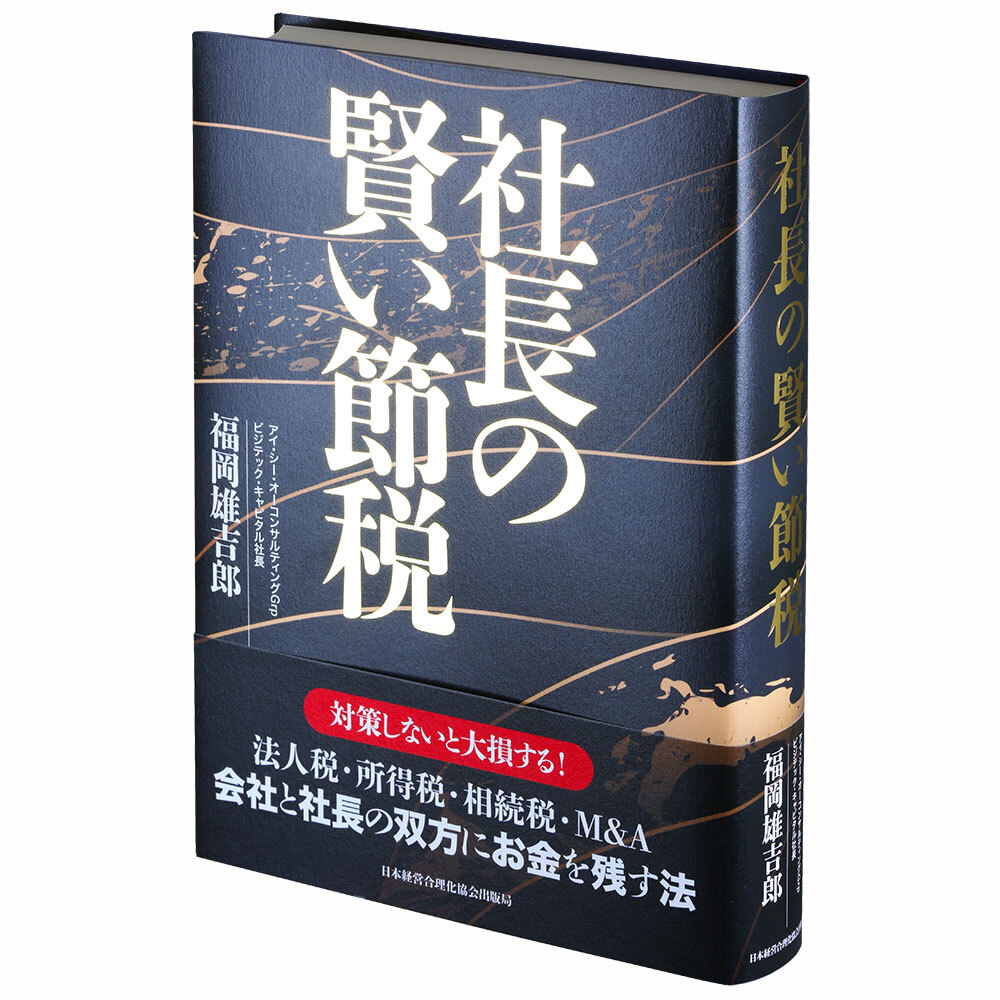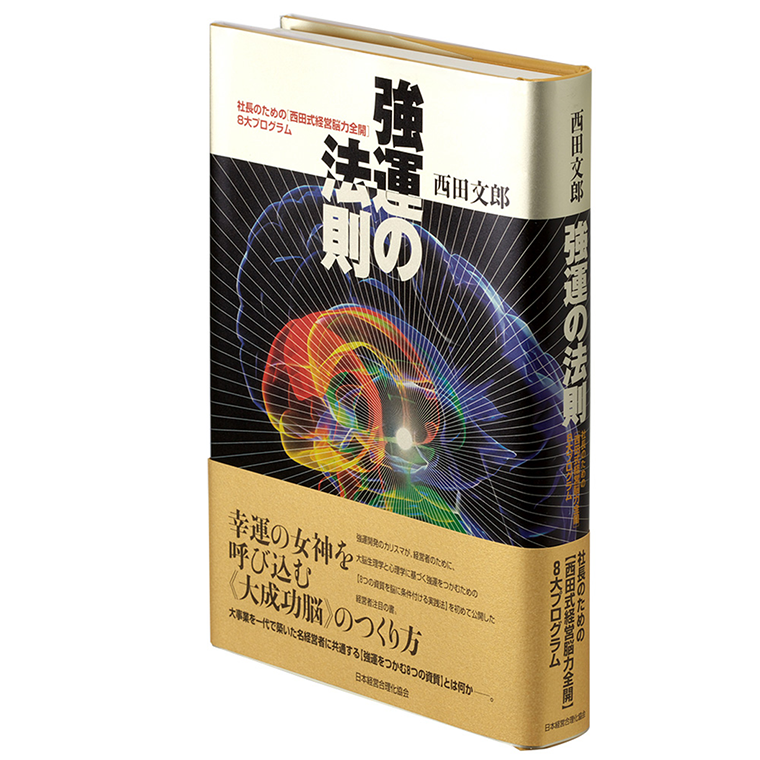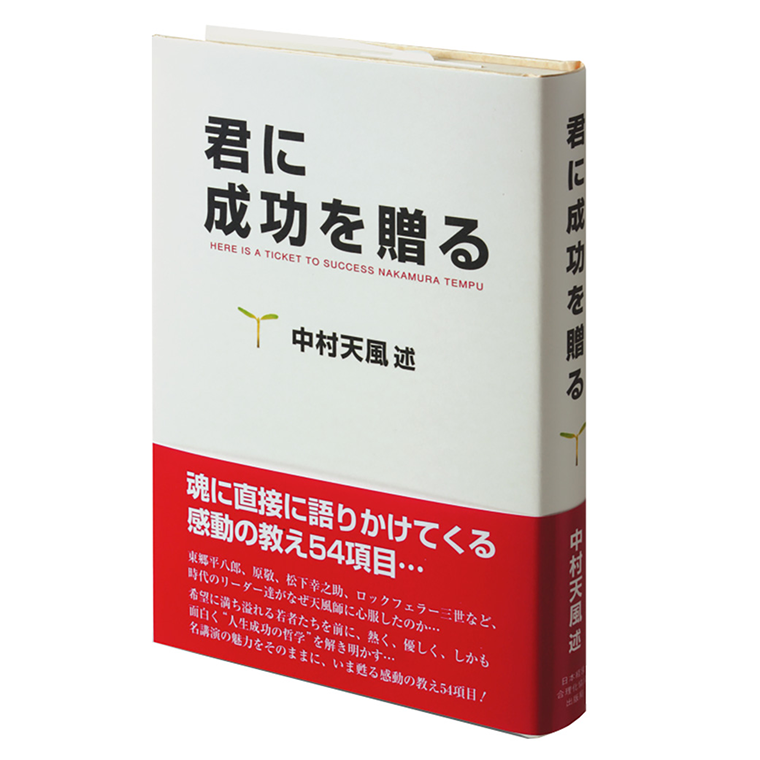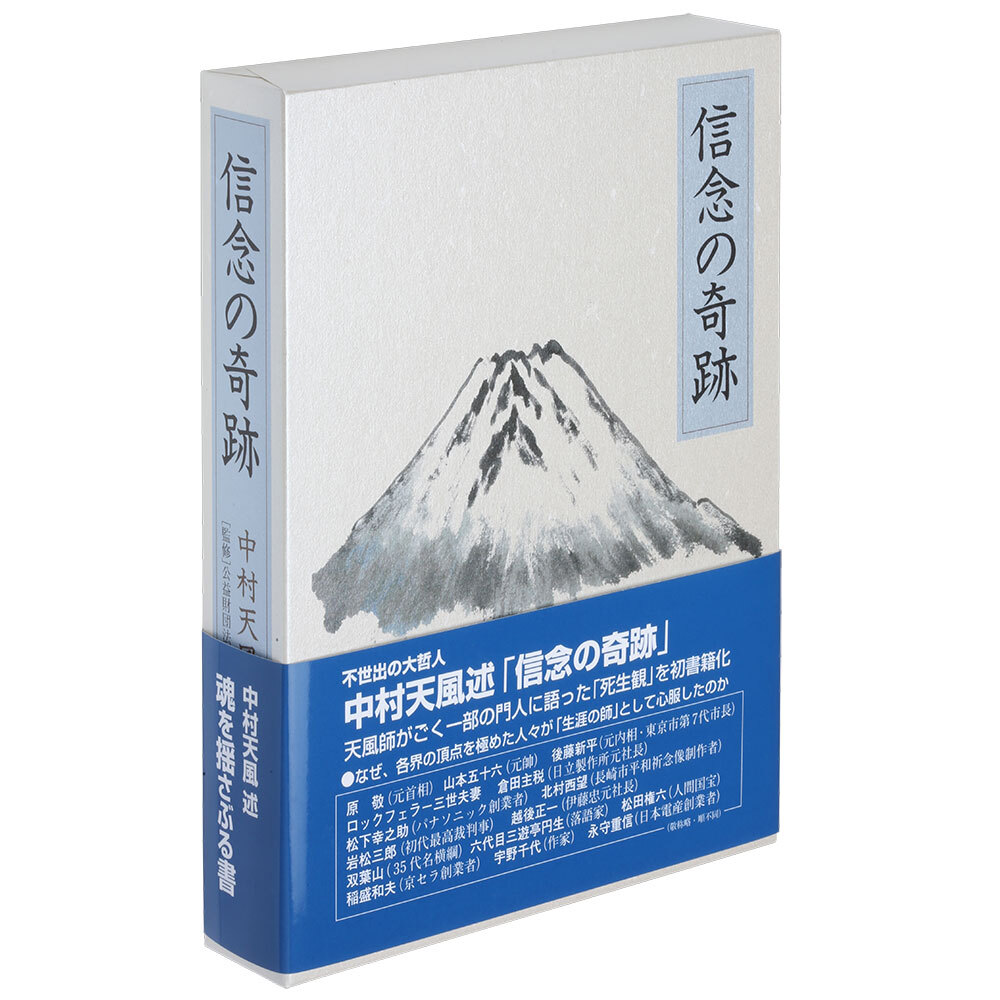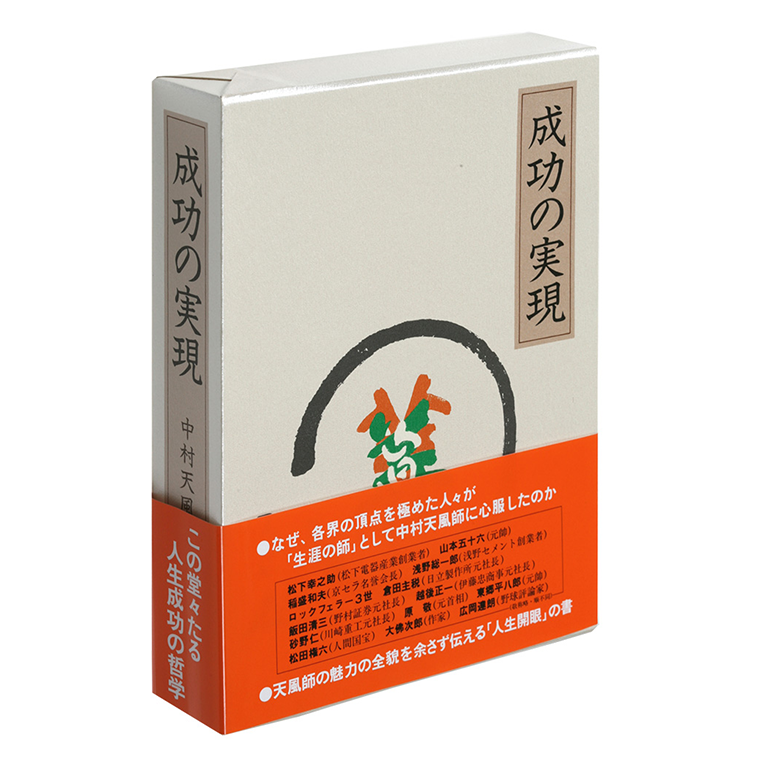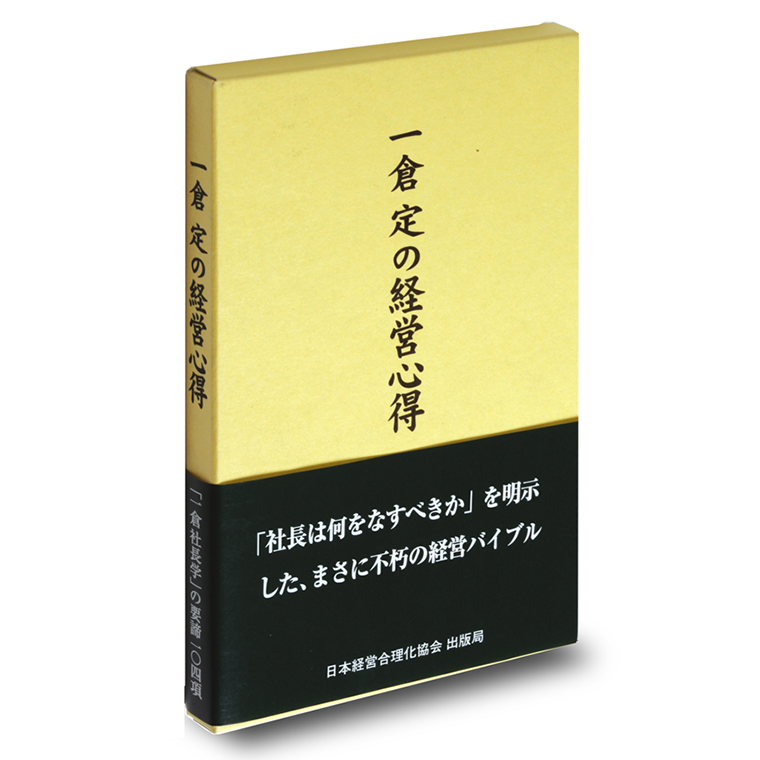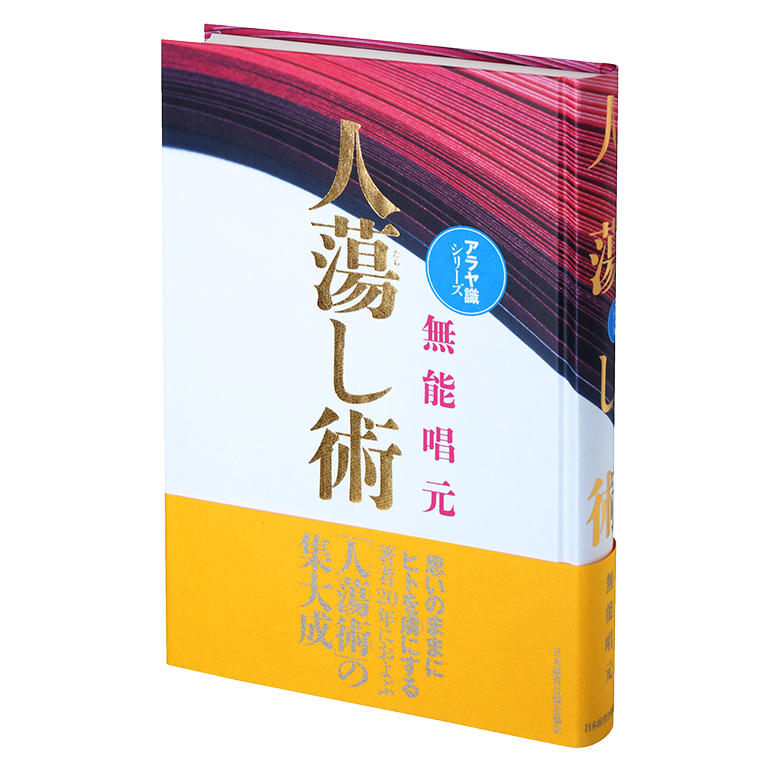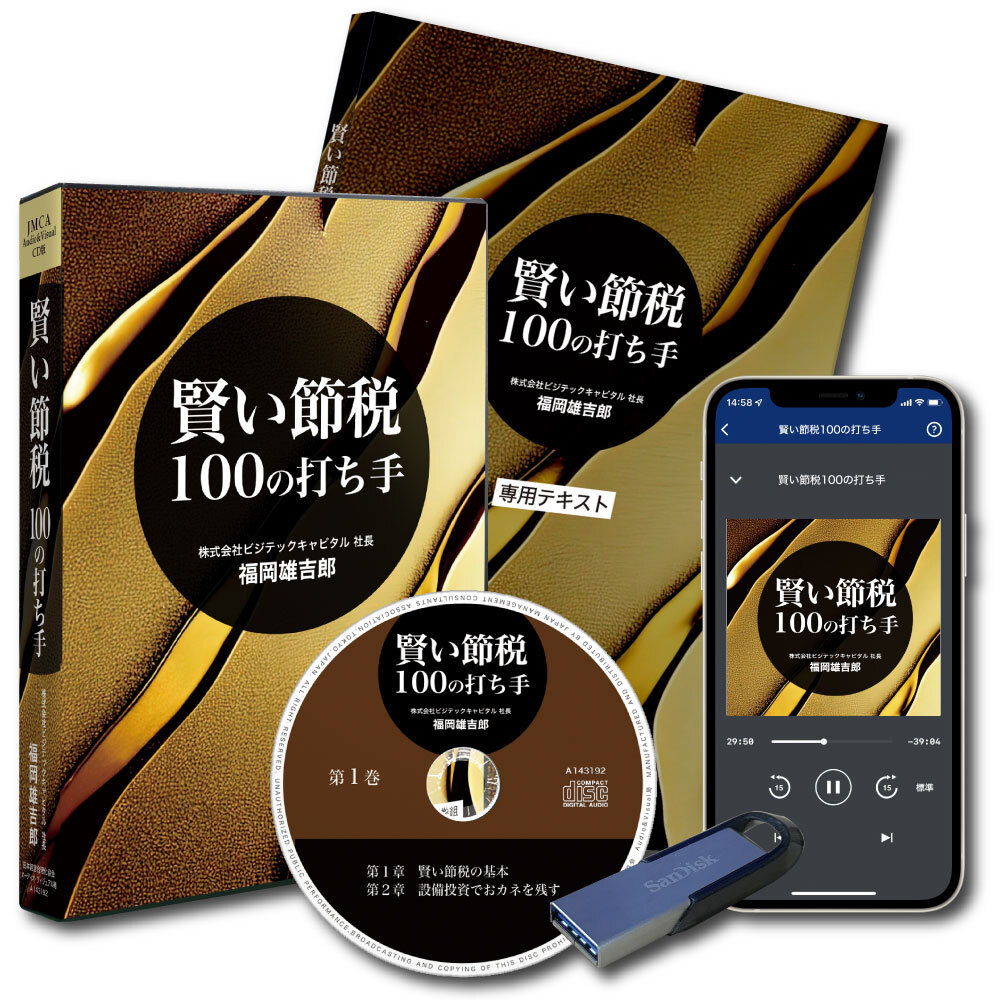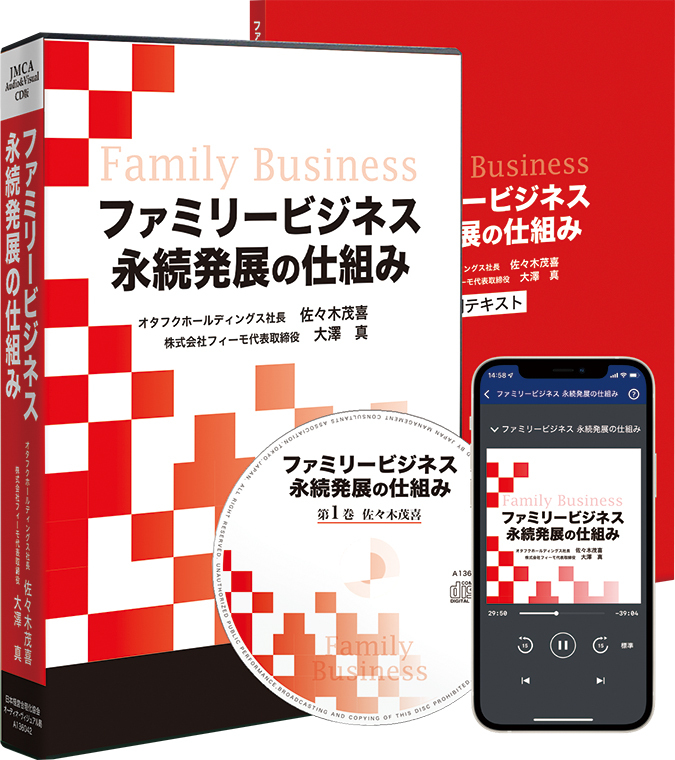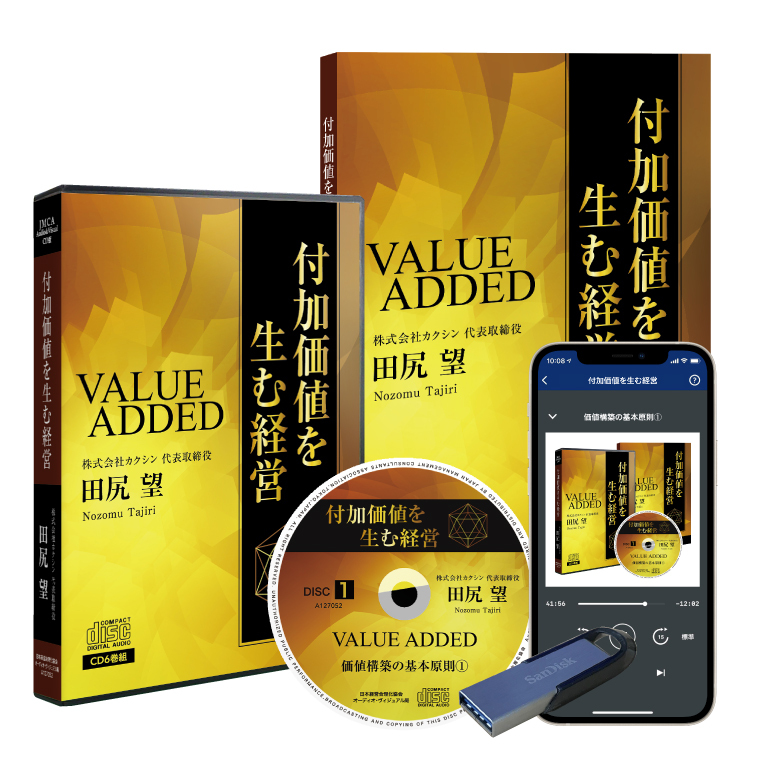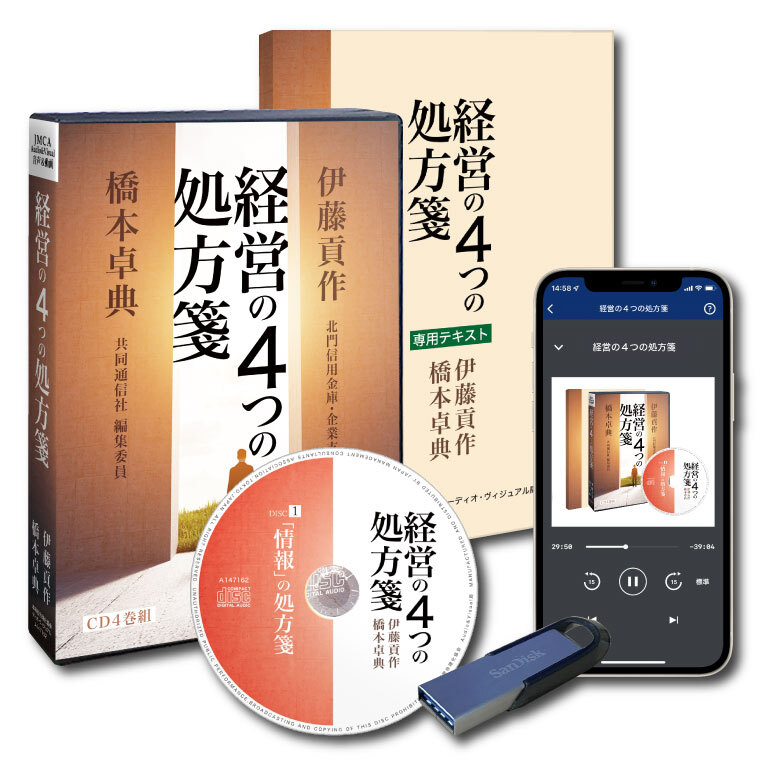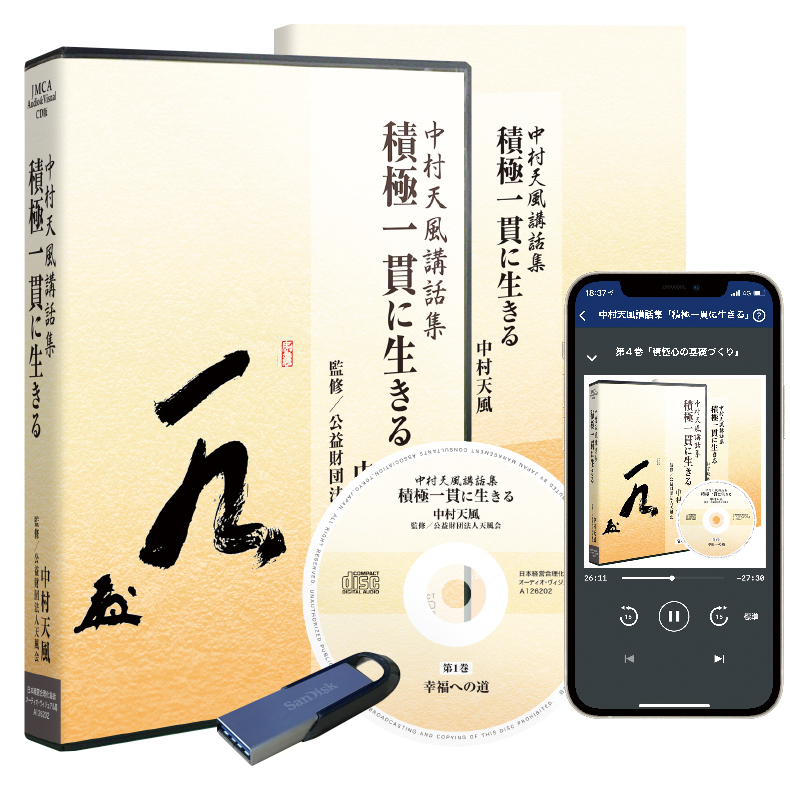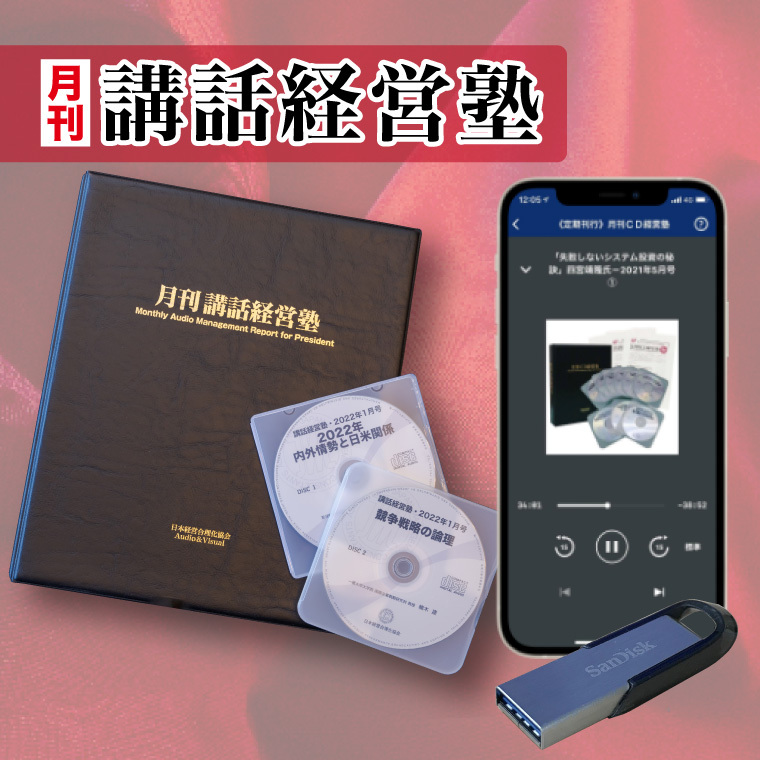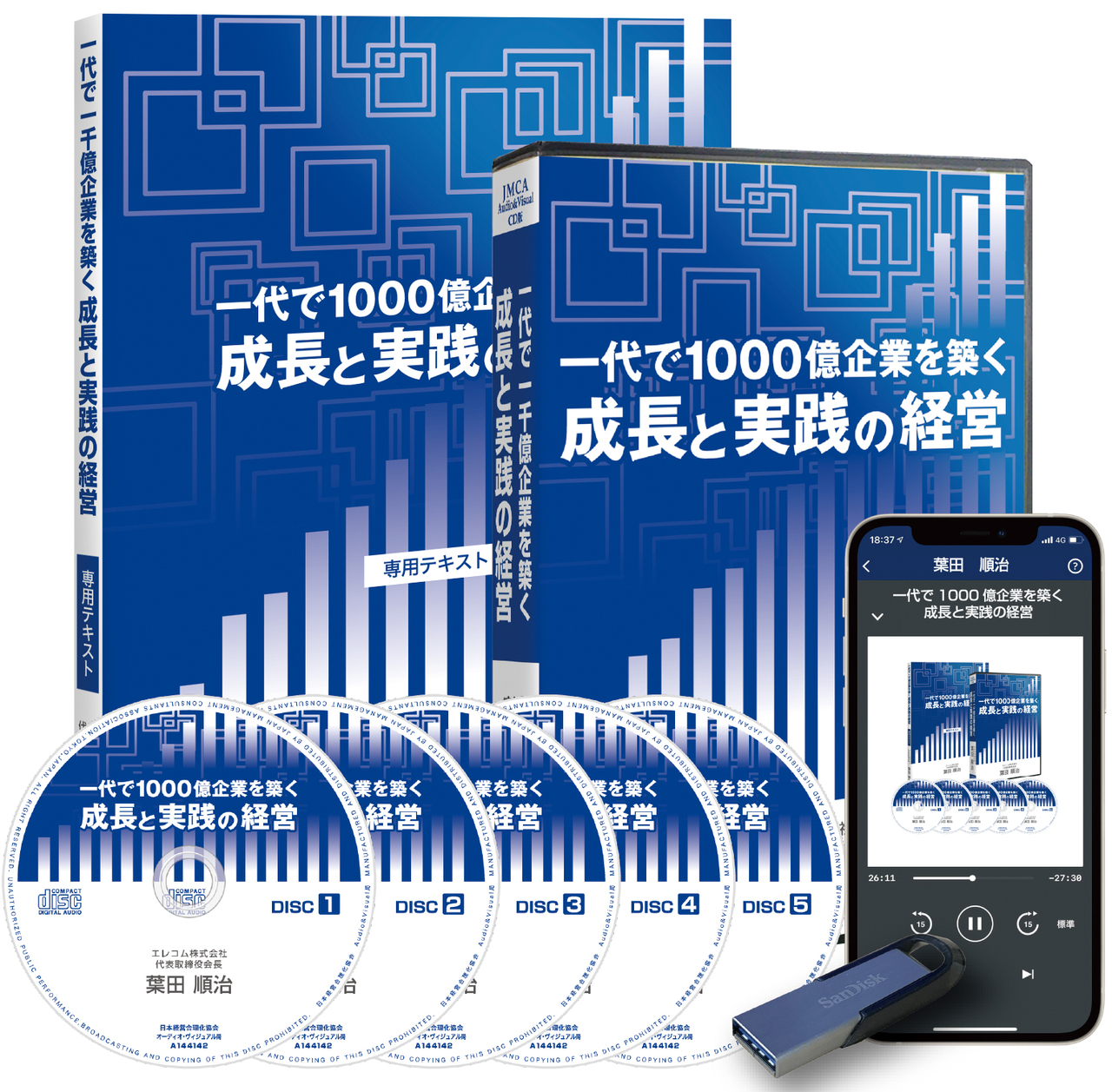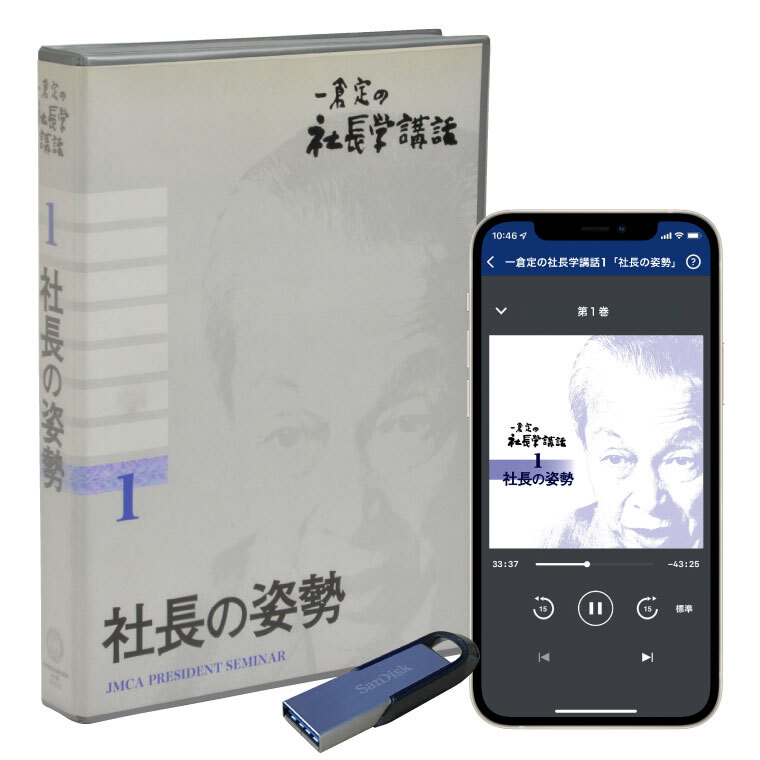新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して「持続化給付金」という制度があります。
大きな影響を受けている証として、ひとつきの売上が前年同月比で50%以上減少していることが必要で、法人の場合は資本金の額又は出資の総額が10億円未満、もしくは、常時使用する従業員の数が2,000人以下であることなどが要件となりますが(詳しくは「持続化給付金」サイトを参照してください)、ひとつきの売上について、税務上注意すべき点があります。
まず「持続化給付金」のサイトの申請方法・必要書類(証拠書類) にある添付書類ですが、法人では、確定申告書類として確定申告書別表一、法人事業概況説明書、2020年の対象とする月の売上台帳、通帳の写しが必要になります。
法人の確定申告書で言えば月別の売上が記載されているもので、かつ、税務署の収受という受付印か、電子申告の場合の完了済・受付番号が押されるのものは法人事業概況説明書しかなく、それによって前年度同月の売上を見て、ひとつきの売上が前年同月比で50%以上減少していることを確認するわけです。
ところで、対象月がちょうど決算月にあたる会社もあると思います。決算月を対象月として売上の半減以上の対象とするとき、決算終了直前に、実質、納品していて請求書もだせるのにあえて翌月の売上にして売上半減条件に適合させようと考えたり、〆後売上、いわゆる納品はしたものの請求をしていない売上があるため、対象月が前年同月比で50%以上の減少にならなくなってしまうので〆後売上を計上しないでおこうと考えたりすることもあるようです。
決算月の請求(売上)の翌月まわしは税務上ハイリスクであるのはもちろんですが、〆後売上未計上についても同様の税務上のリスクがあるのです。〆後売上未計上については決算確定前に、法人税基本通達2-6-1(注1)を確認して、〆後売上じたいを決算の数字から除外しても税務上問題はなさそうだと考える人もいるようですが、
実際には、このことは税務上きわめてリスクの高い行為になってしまいます。
同通達はそのような行為を認めているとも読めるのですが、「継続して」という文言が通達の文言にあるからです。
税務上は多くのことに継続適用という原則が適用されていて、一度決めた基準は合理的な理由なく変えることができないのです。
例えば、前期は納品したときに売上を計上していたのに、今期は納品、検収したときに計上するといった会社の都合で、売上の計上時期が操作されるのを防ぐために継続適用が求められるのです。
こんなふうに、税法条文や通達の多くが、恣意的に利益を操作することを防ごうとして規定されているのです。
(注1)法人税基本通達2-6-1
(決算締切日)
法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。