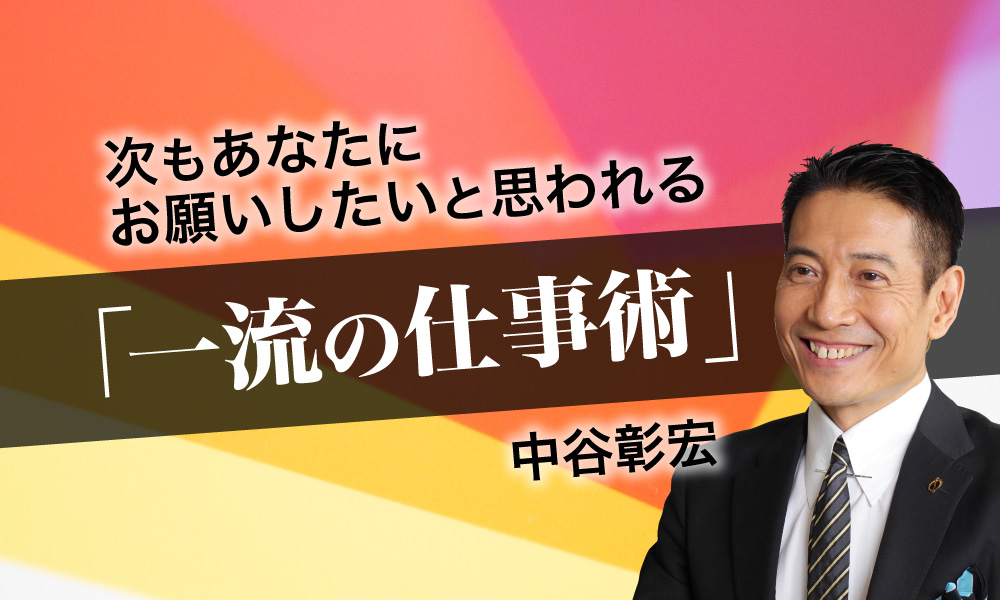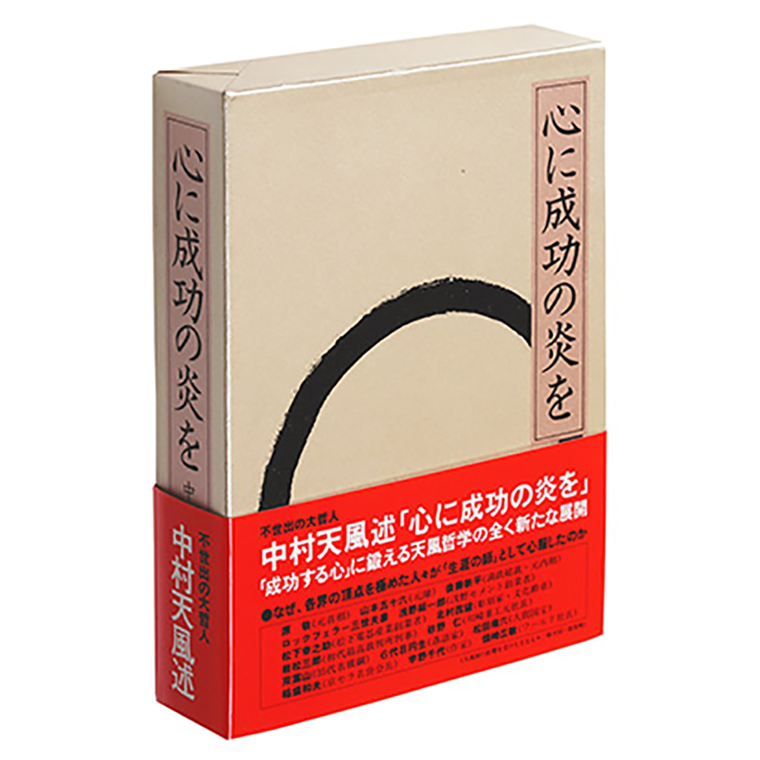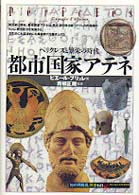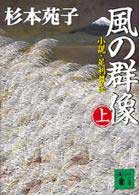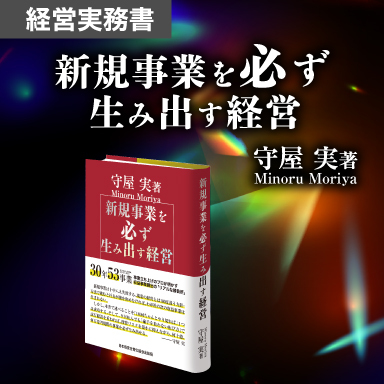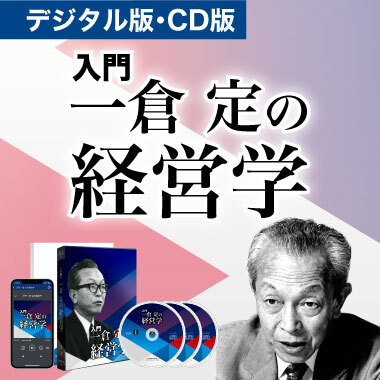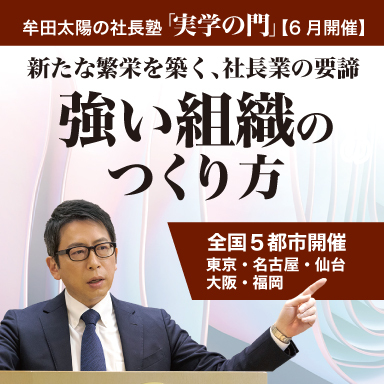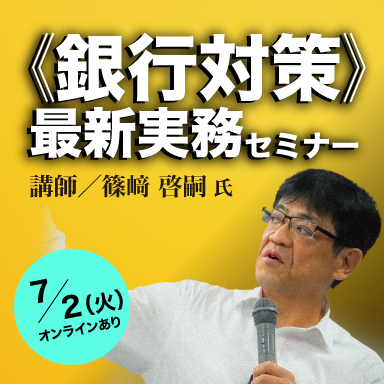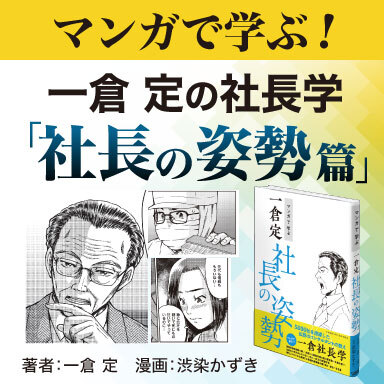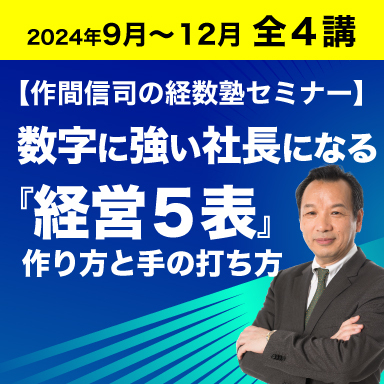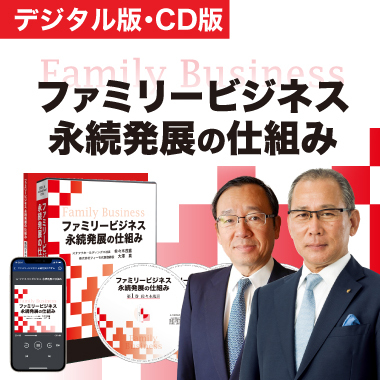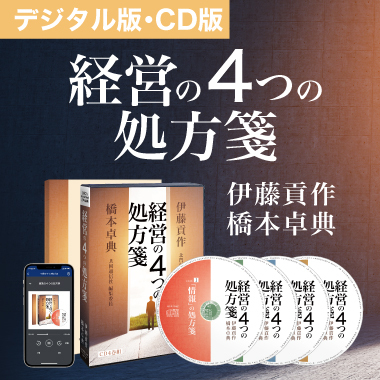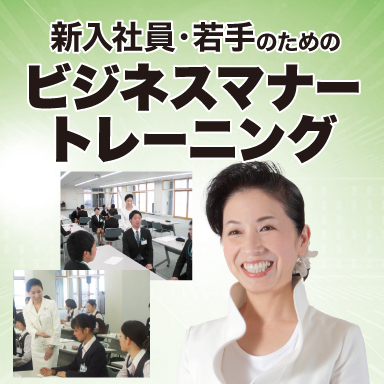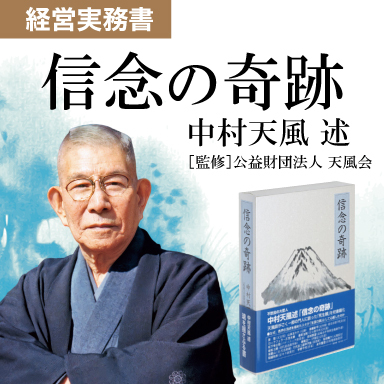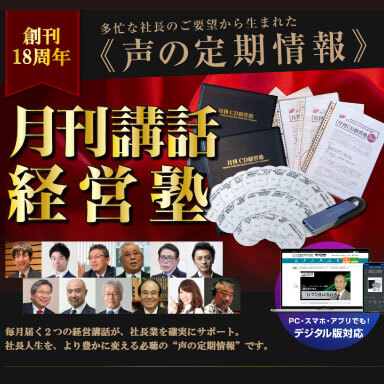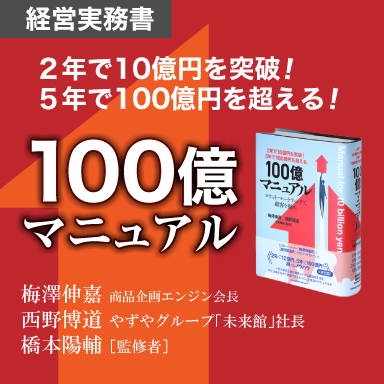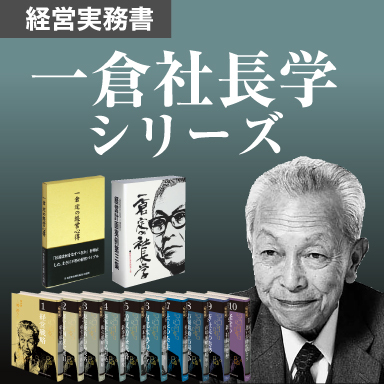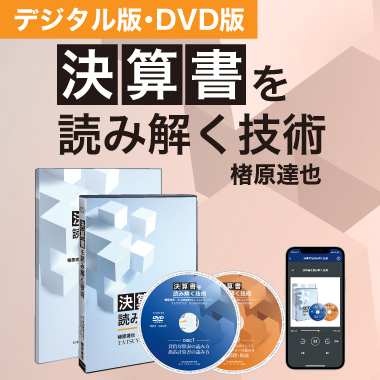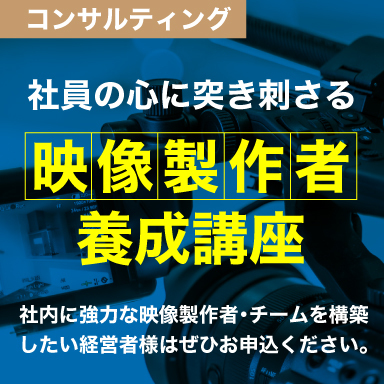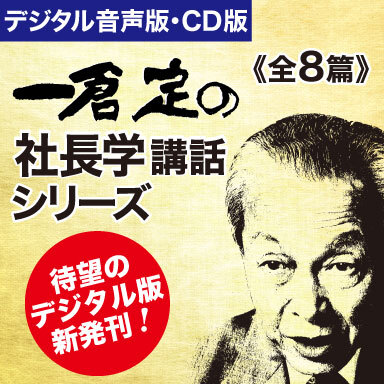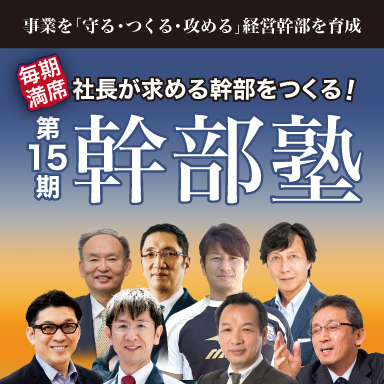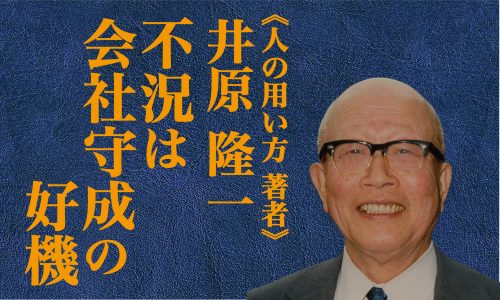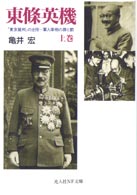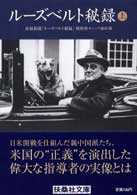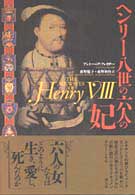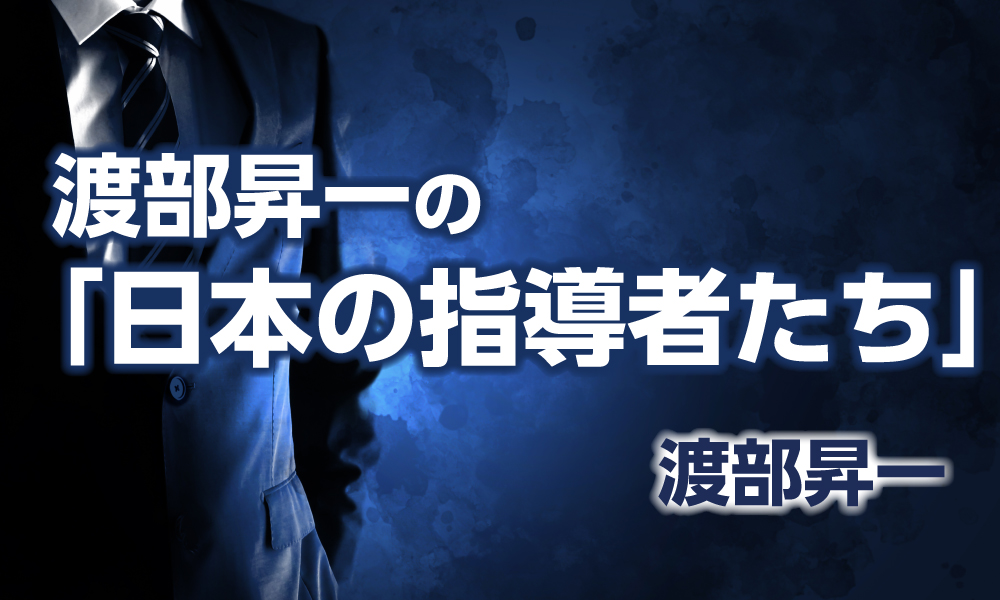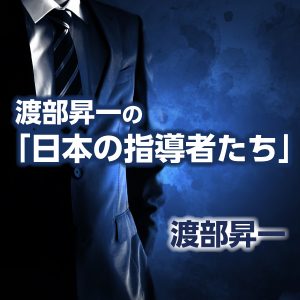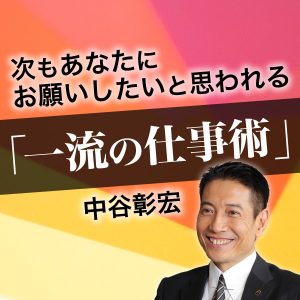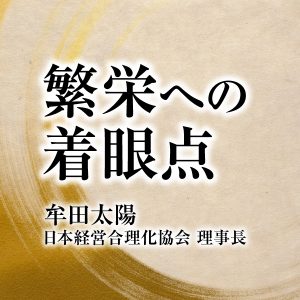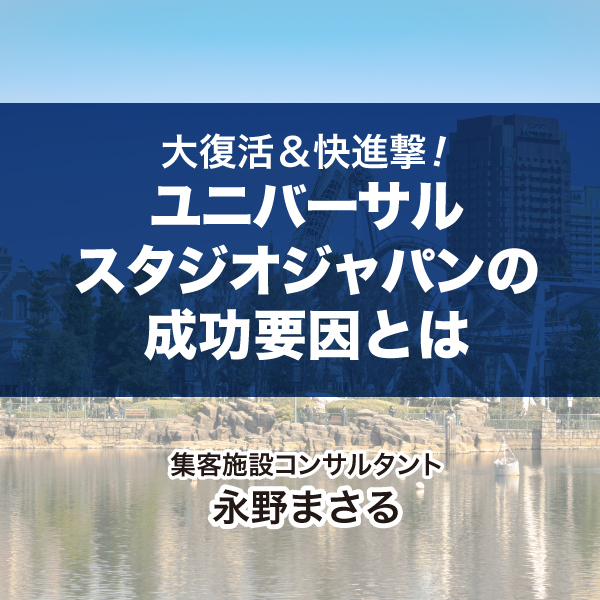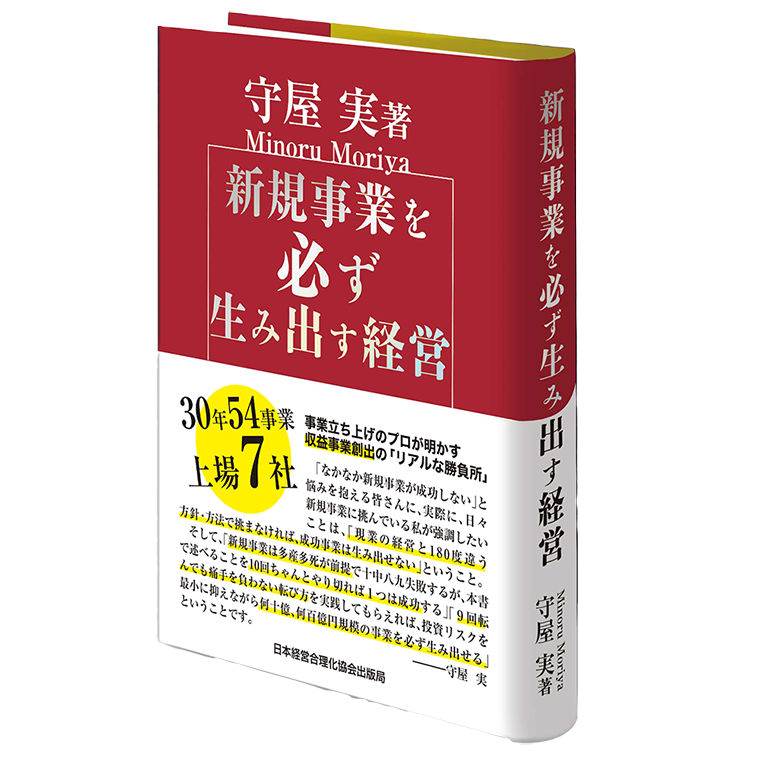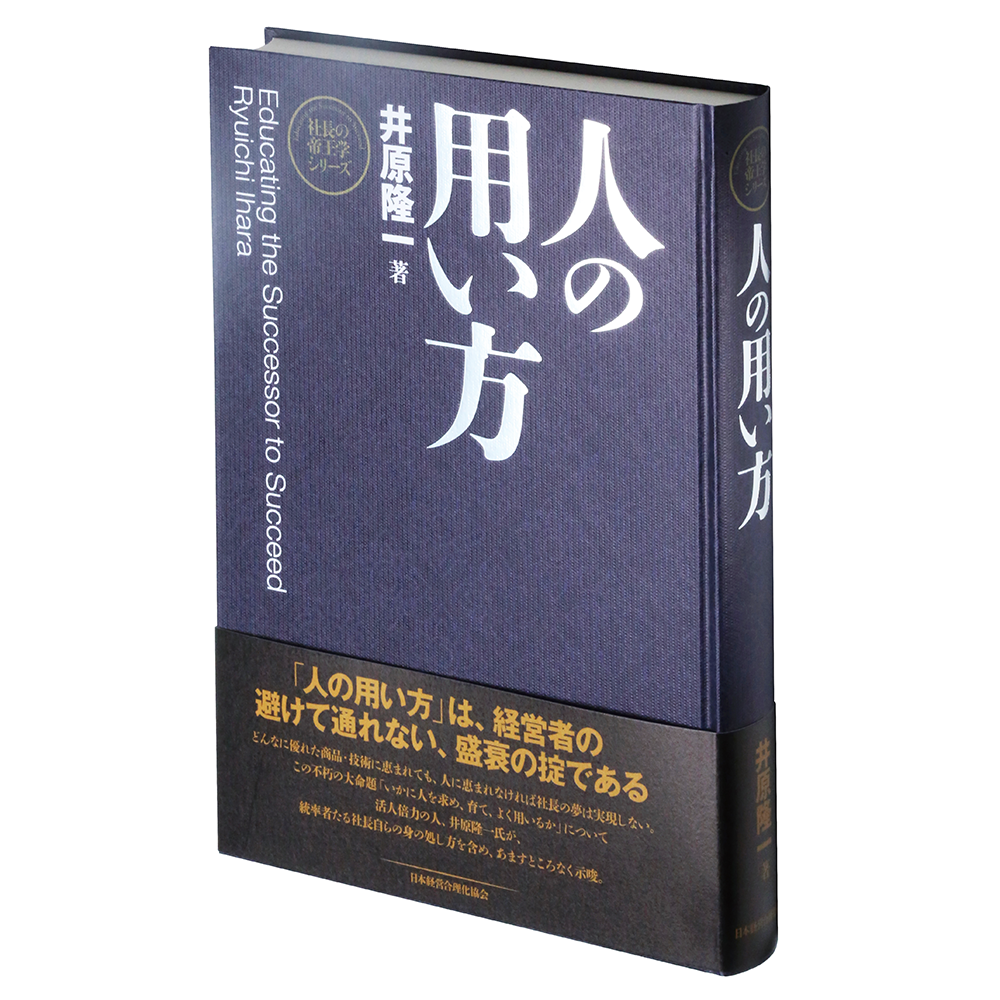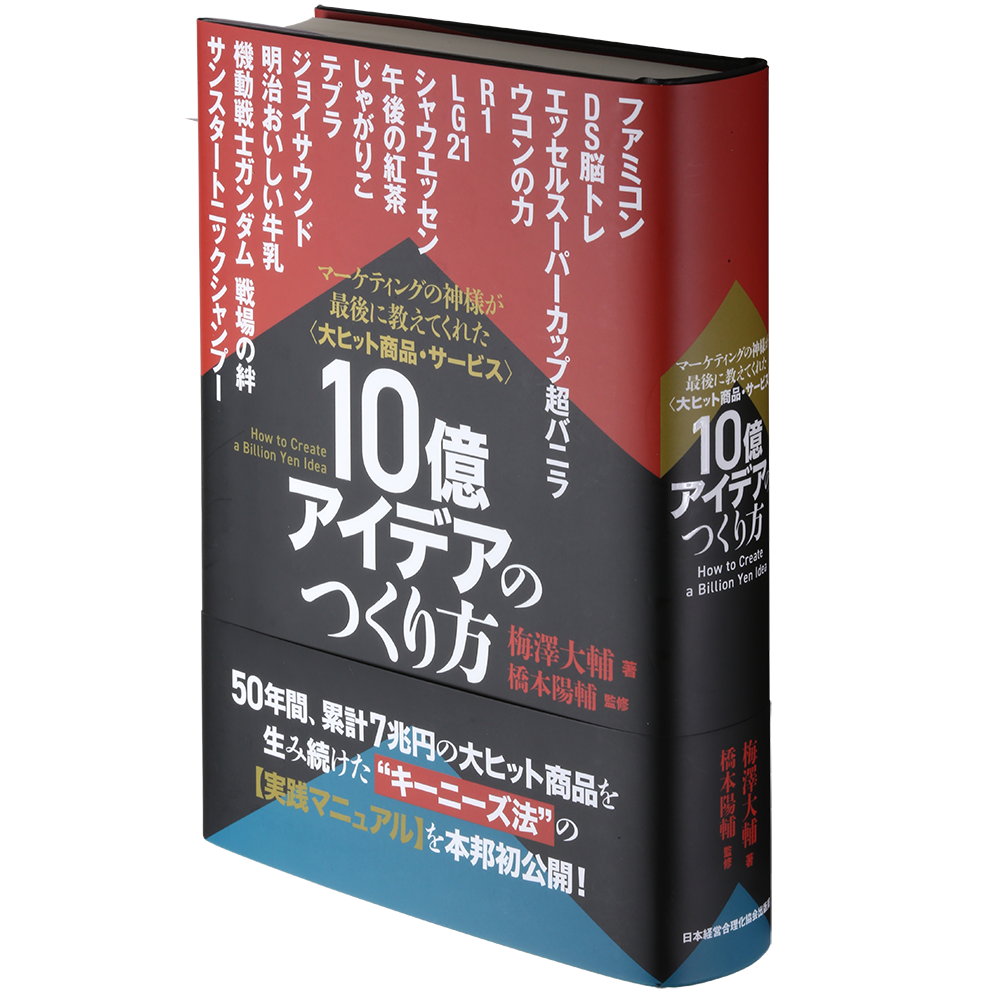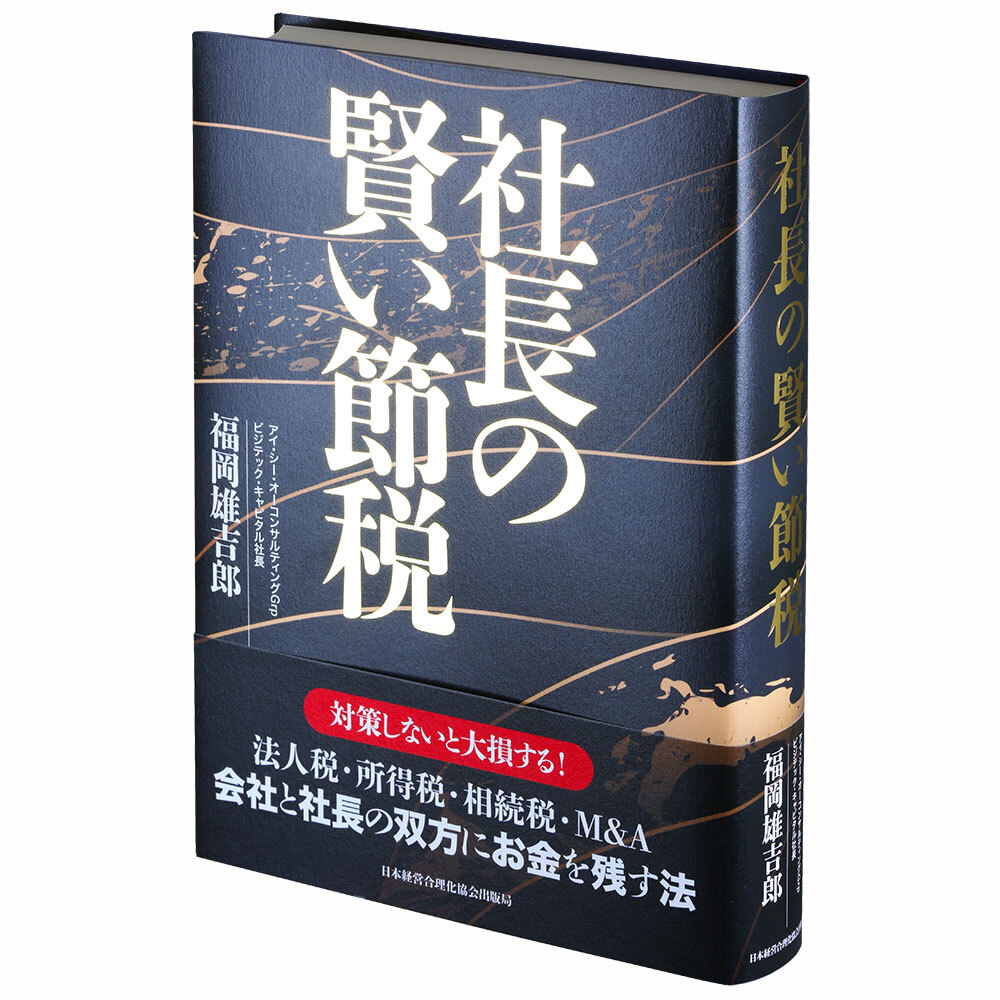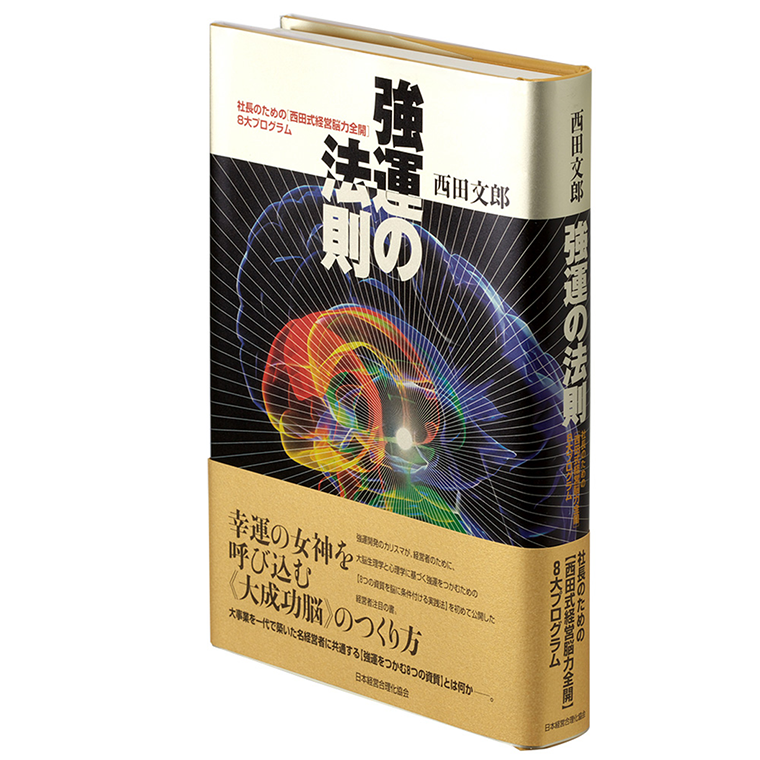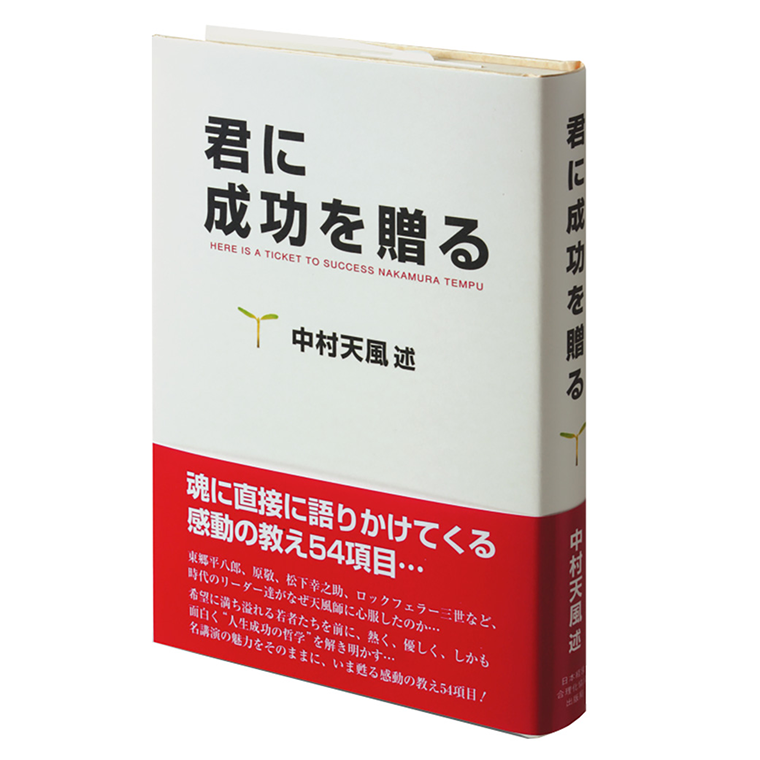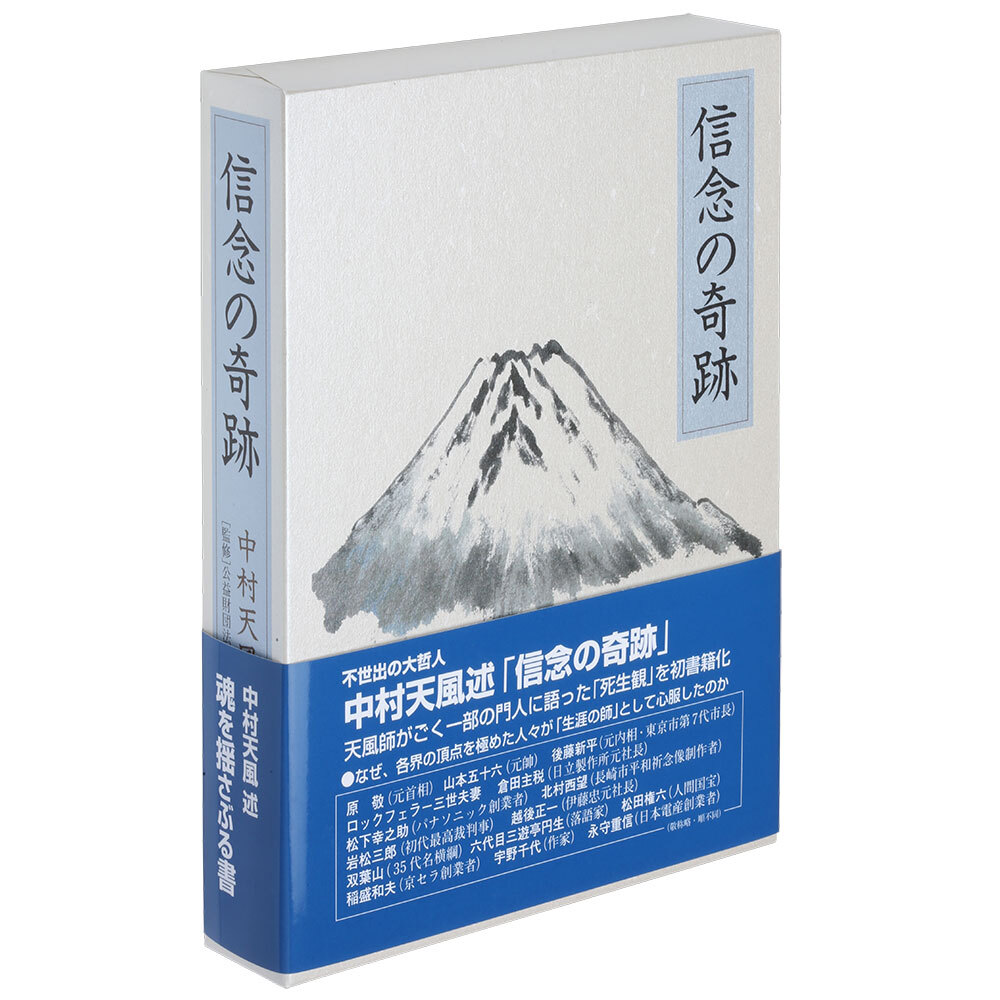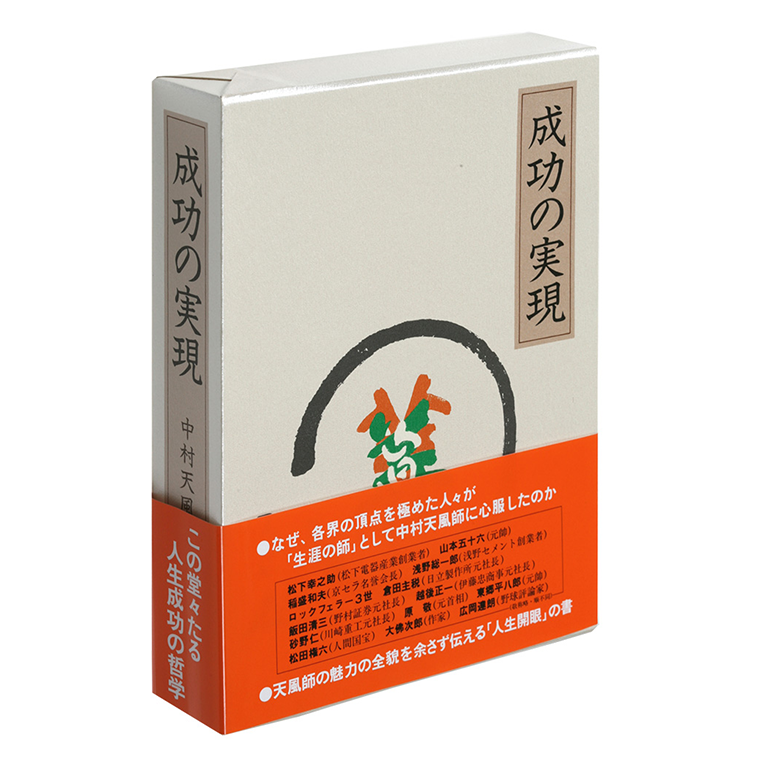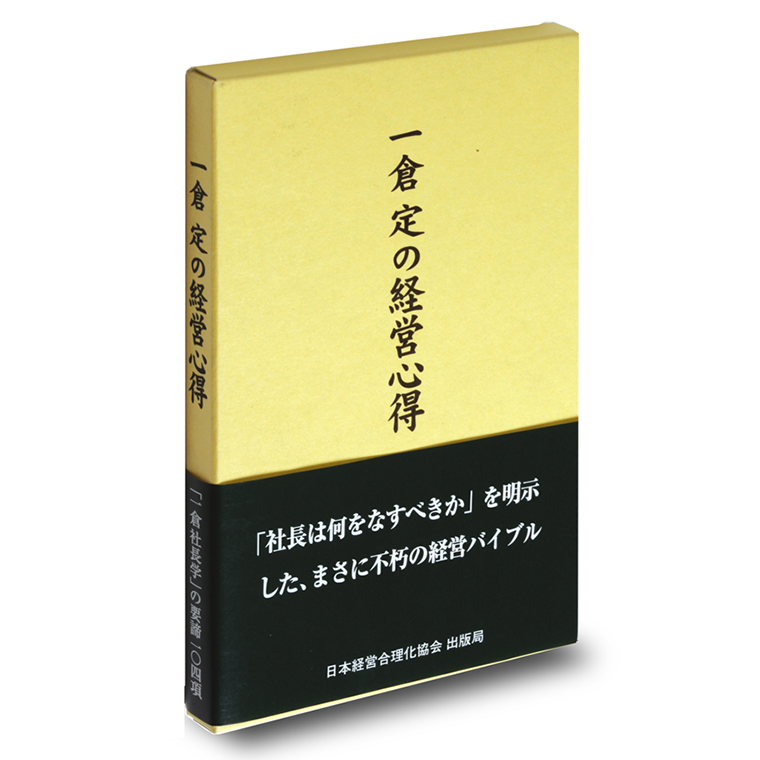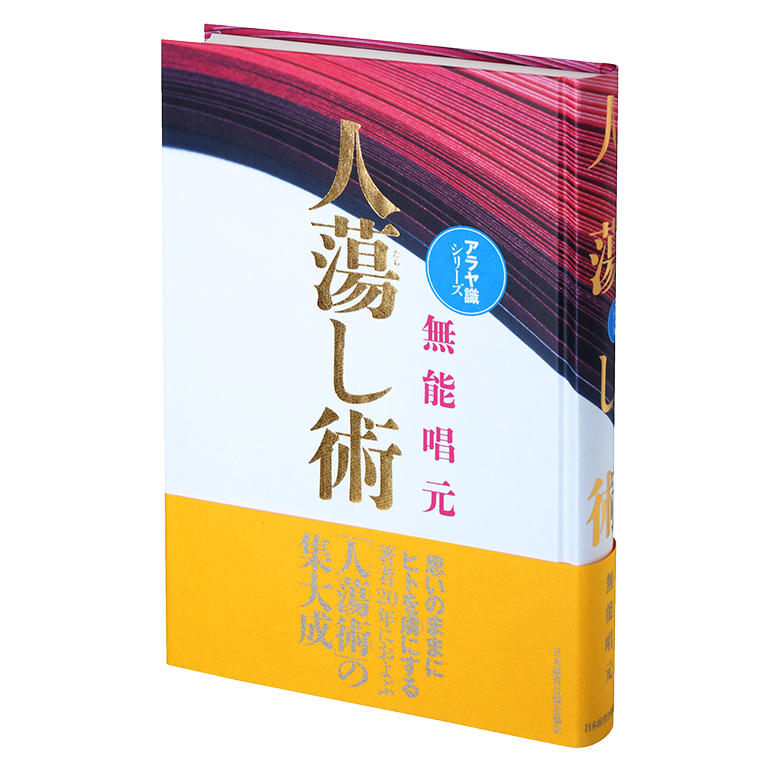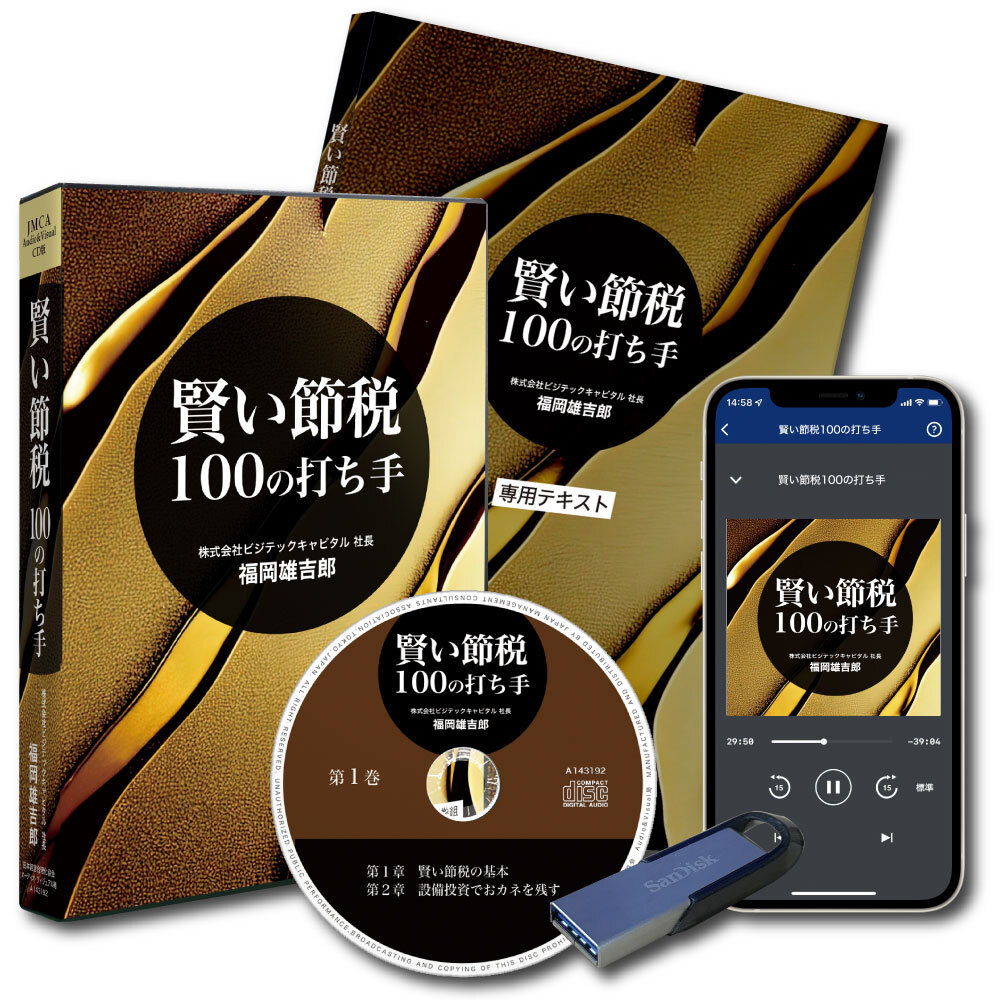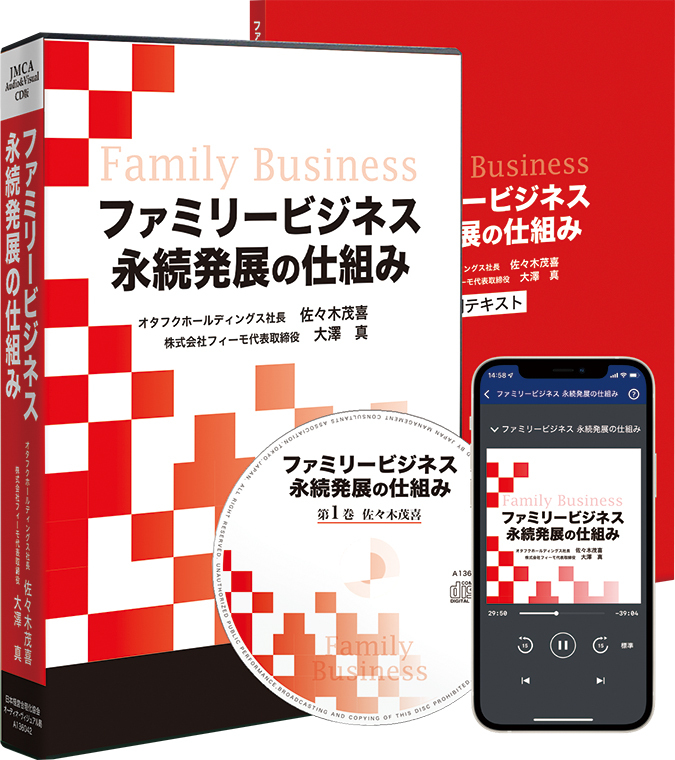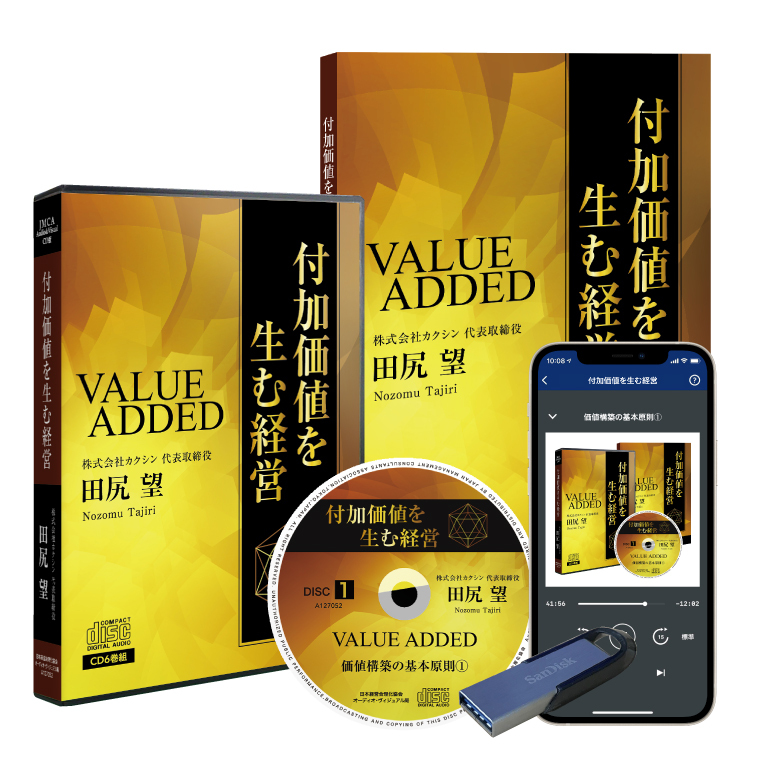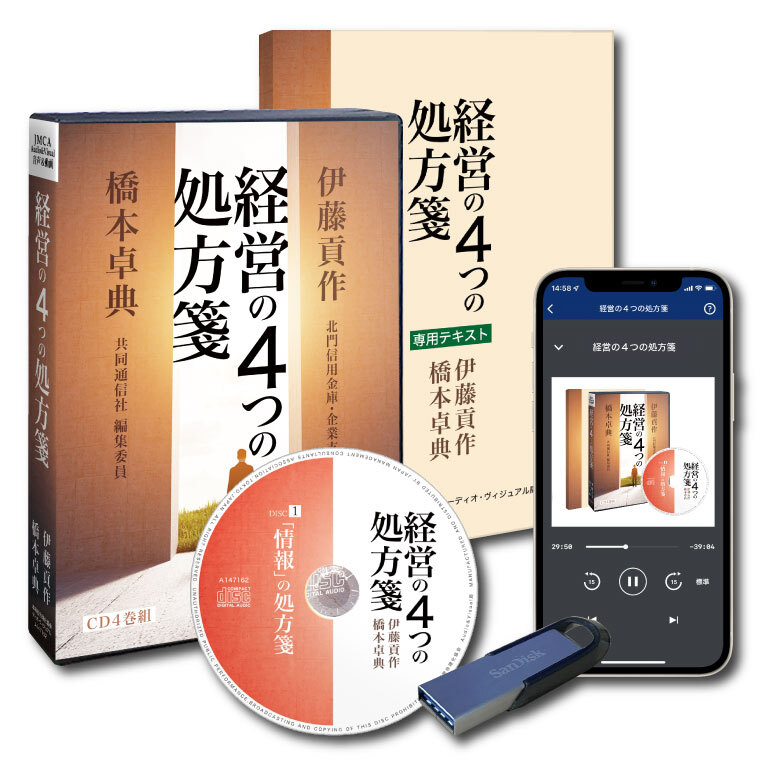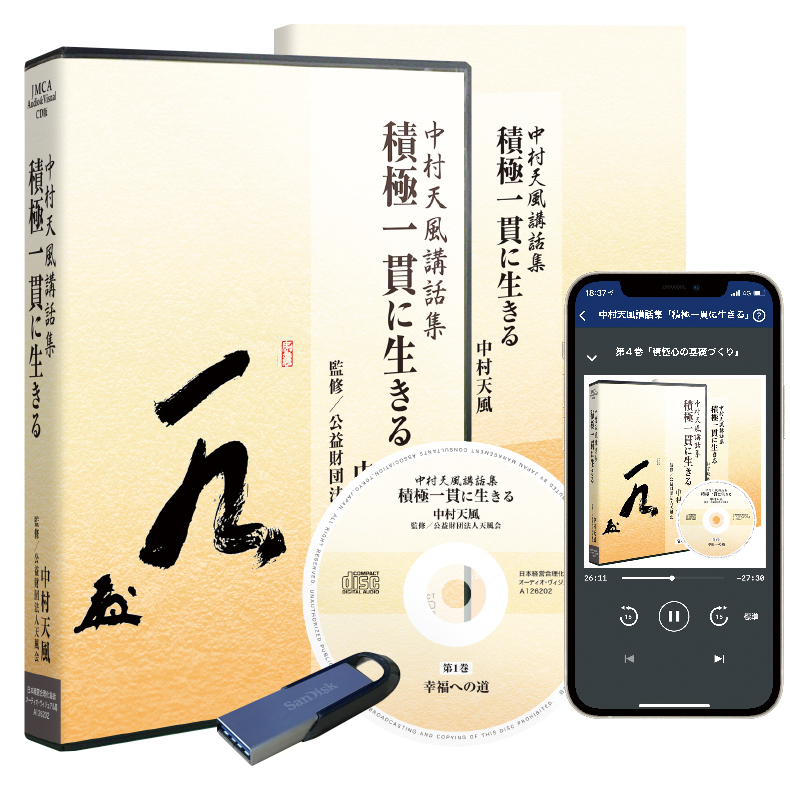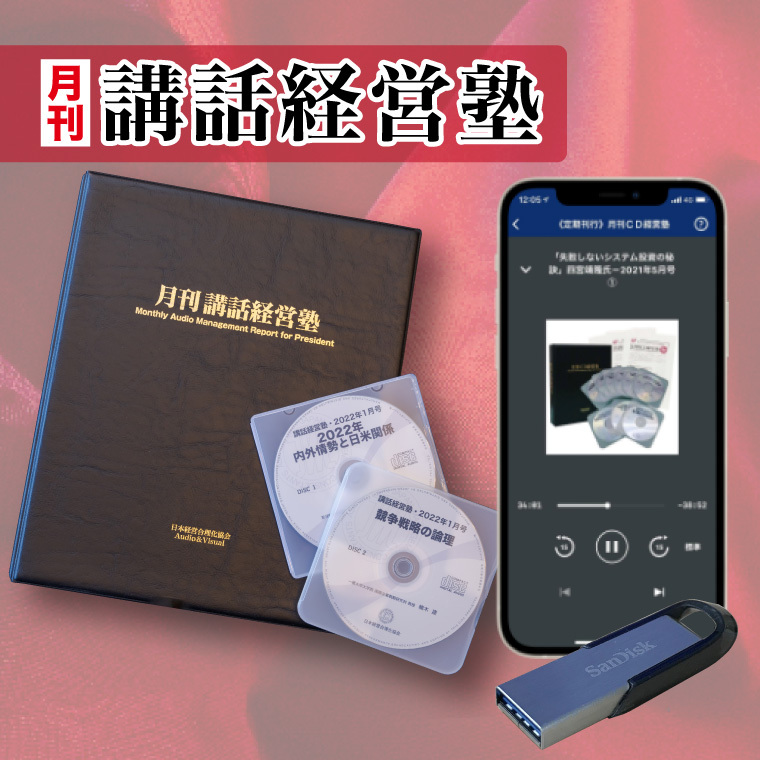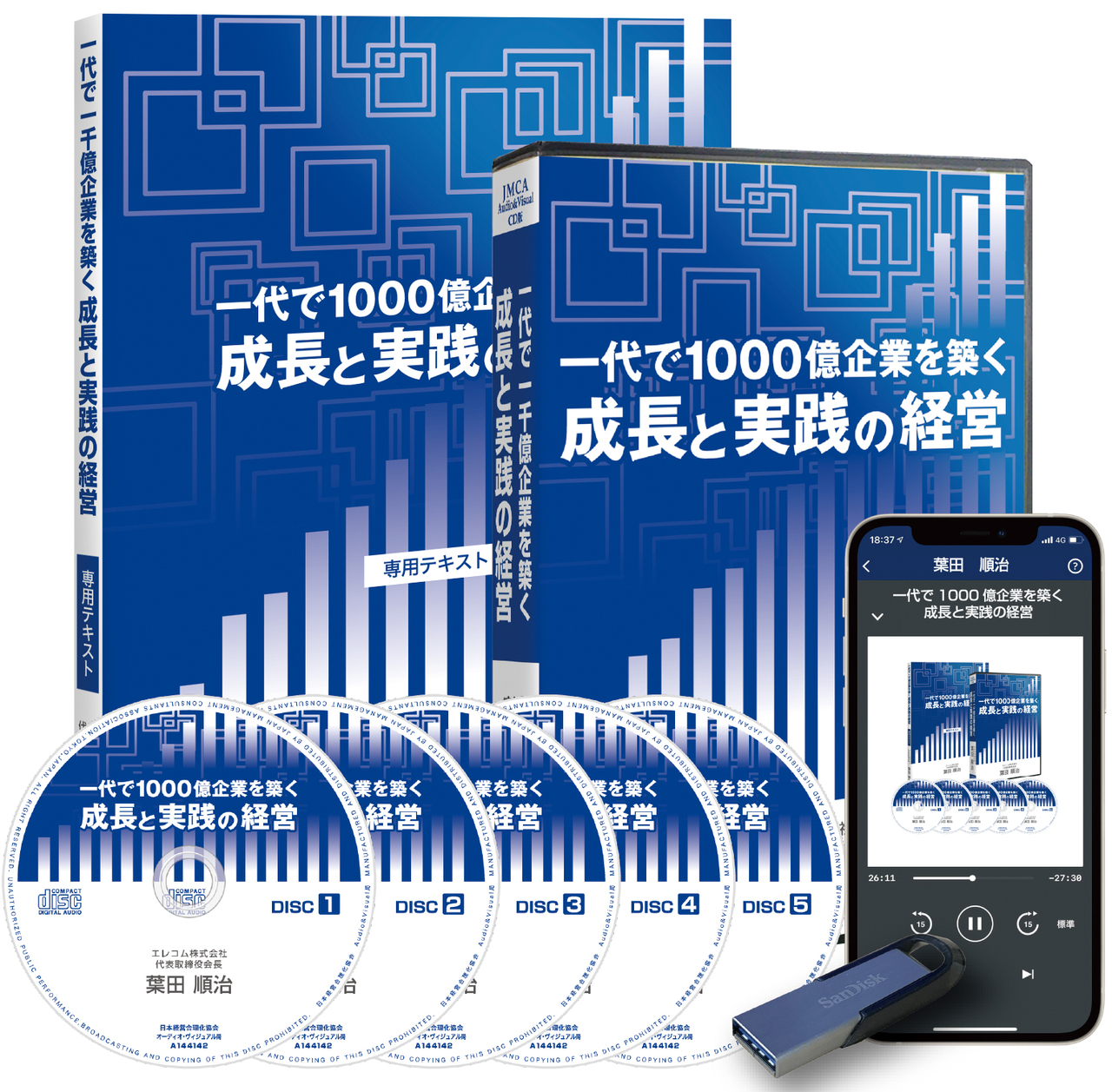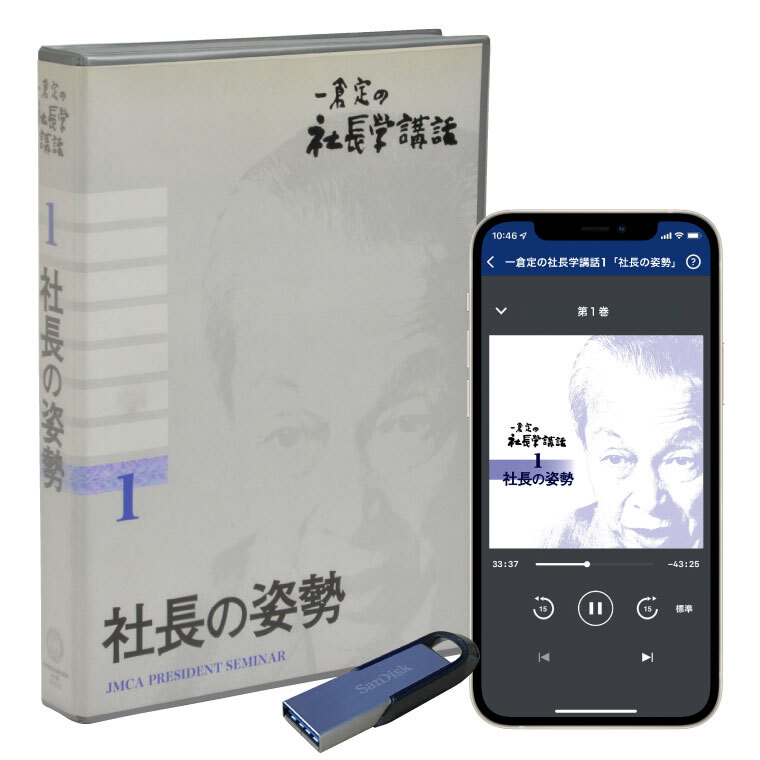子供の頃に読んだ『キング』に博文についての逸話があった。戦前のこの講談社の国民的大雑誌には偉人についてのエピソードがよく掲載されていたものである。その話というのは次のようなものだった。
ある政治家が料亭に行ったら、藝者が「また大きな戦争でも起るのですか」と聞いた。その政治家が「なぜそんなことを聞くのか」と問い返すと、その藝者はこう答えた。
「伊藤博文様はよく藝者のひざ枕でくつろがれ、すぐ眠られます。しかし大きなことがある前は、目を閉じては開き、閉じては開き、眠りこむことはありません。近頃はいつもそうです。何かお国の大事件でもあるに違いありませんわ。」
あの頃の政治家たちは料亭で藝者の踊りを見たり、自分も端唄を歌ったりしてくつろいだり、また政治の密談などをした。幕府を倒す相談も、維新の志士たちは料亭や遊里でそうしてきた。
その理由の一つは、各藩から京都や江戸に出てきた志士たちの集まれる場所が料亭以外にはほとんどなかったからである。その習慣は明治政府になっても続き、それは江戸時代の各藩の江戸留守居役同士のつき合いの慣習とも合致し、料亭は日本の政治と切り離せないものになっていた。
フランスのサロンとか、イギリスのクラブなどと一脈通ずるものがあった。そこに働く藝者は、一流の料亭では一流の藝者で、藝も達者で頭もよかったが、お客の政治・経済の話は聞いても耳に入れない訓練がされていた。
密談が料亭から洩れることはまずなかった。洩れたらその料亭はつぶれるおそれがある。(戦後でも、赤坂の某料亭の下足番が、お客の名前をマスコミに洩らしたため、その料亭の女将はノイローゼになり、後になくなった。)
伊藤は維新の志士である。今の基準で「藝者のひざ枕」を批判してはいけない。重要なのは、伊藤は朝から晩まで日本のことを考えていたことである。
この時は日露戦争の前である。ロシアが朝鮮半島全部を支配し、隠岐・対馬のすぐ目と鼻の先の鎮海湾に軍港などを作ろうとする動きを見過ごすべきか、決戦すべきか。藝者のひざを枕にしていても眠りに落ちることはできなかったのだ。
伊藤の一生を貫いた特徴は「お国が第一」ということでそれについては一点の疑問もない。幕末の頃、伊藤ら五人は長州藩から金を出してもらってロンドンに渡った。船では水夫の役をやらされひどい目に合ったりもしたのであるが、ロンドンでは英語の勉強にうちこんだ。
伊藤は以前に長崎に洋式兵法を習いに行った時から英語の勉強に熱心だった。そしてイギリスから世界を見て、攘夷などできるわけがないと悟った。世界の大勢に開眼したのである。ロンドンで一年ほど経った時、長州や薩摩が外国船を砲撃し、戦争になりそうなことを知ったのである。
「こうしてはおられぬ。絶対に欧米と戦ってはならぬことを説こう」と伊藤と井上馨の二人は帰国する。他の三人は「自分たちは西洋のことを勉強するように命じられてきたのだから帰らない」と言ってイギリスに残った。
自分の祖国が危いことをやろうとしていることを新聞記事を読んで、すぐに帰国を決行するところが伊藤と井上の偉いところである。攘夷勢力の強いところに帰れば暗殺される危険も高い。
しかしそんなことを言ってはおれない、という気持ちが強いのだ。事実、井上は帰国後は暗殺団に襲われ瀕死の重傷を負っているし、伊藤も何度か危なかった。
伊藤は若い時は血気盛んな志士で、何度も暗殺に加わっているし、また品川の御殿山の外国公使館の焼き討ちにも重要な役割を果たした。そういう血の気の多い博文は、年を取るにつれて、着実に慎重になる。
大久保利通が暗殺された後は、伊藤を中心に明治時代が進行するが、それは伊藤の考え方が慎重緻密であることがみんなに認められてきたこと、特に明治天皇が「伊藤が一番安心できる」と信頼されたからである。
初代首相、初代枢密院議長、明治憲法の起草者として伊藤は誰から見ても元勲中の元勲であった。
しかし彼は自分のメンツより国のことを重んずる人であった。日露戦争は避けるべきだとし、日露協商論者であった。ロシアを説得するためにヨーロッパに出かけた。
その間に、イギリスからの提案もあり、日英同盟が成立する方向になり、伊藤は浮き上がった形になった。彼は日本の国力を考えてロシアとの戦争はあくまでも避けたかった。
しかし最終的には開戦を決心する。そしてアメリカ大統領ルーズベルトと同窓生であった金子堅太郎をアメリカに派遣して平和條約の下準備をさせる。開戦前から終結の工作を始めさせているのだ。この前の戦争の指導者と比べてもみよ。
最も大きな政府側の権力者でありながら、自ら政党の党首となるのである。コレが原敬に至るまでの日本の民主主義の本流となった。朝鮮を植民地にすることにも反対であったが、彼の意向を挫いたのは朝鮮人たち自身の動きである。
また子供を政治家にしなかった。「政治家の世襲は幕府時代と同じではないか。われわれはその幕府を廃止したのだ。また再び幕府みたいになっては維新で死んだ人たちに申し訳がない」という考えだったようである。そう言えば維新の元勲に二世政治家はいない。
渡部昇一
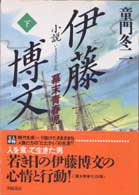
〈第19人目 「伊藤博文」参考図書〉
「小説 伊藤博文」上下巻
童門冬二著
学陽書房刊
本体各660円